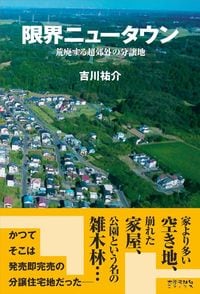地域社会から顧みられることもなく、一度は打ち捨てられようとしていた「住宅地」を、みずからの手で再生させていき、自身の拠点として整備を進めていくその達成感は、ほかではあまり味わうことのできないものだと思う。
もちろん、それはけっして楽な作業ではなく、とくに夏季などはあまりの暑さに音を上げてしまうことも多々あるのだが、みずからの手で住環境を維持しているという実感はまちがいなくある。
僕がこれまでブログなどで、限界分譲地を利用するうえでの魅力をあまり語ってこなかったのは、この感覚がきわめて個人的な漠然としたもので言語化しにくかったからであるが、土地整備を進めていくうえで得られるこの充足感こそが、限界分譲地のいちばんの魅力なのだと、いまは考えている。
両親が持てなかった「自分の根城」
そのような充足感を僕が強く求めるのは、おそらく僕の両親がともに「実家」というものをもたず、戦後から近年まで、住まいのことで苦労しつづけてきた家で育ったからだと思う。
父は中学卒業までを児童養護施設で生活しており、生家がない。また、母方の祖父は南満州鉄道の社員として、戦前から戦中、祖母とともに旧満州国の奉天(現・瀋陽市)で暮らしていたため、日本国内に住まいを持っていなかった。
終戦まぎわに徴兵され、引き揚げ後は長く公営住宅で暮らした祖父母の戦後は、生活の再建で精一杯であり、やがて復興とともに到来した開発ブームからも置き去りにされ、祖父母は結局、最期まで自分の家を持つことができなかった。
そんな祖父母や両親を見て育った僕は、生活の根幹である住まいのことをいいかげんに考えることはできないし、どんなに粗末で、どんなに不便であろうと、やはり自分の根城というものを保有したい思いが人一倍強い。
住まいに関しては、自己裁量の幅が限られて他人まかせの要素が大きい場所だと、かえって安心できないのだ。
そして、限界分譲地での暮らしこそ、まさに己のもつ最大限の力を駆使して、あまたあるデメリットをカバーする暮らし方であり、僕は、非力で不器用でありながらも、そういうところでしか暮らすことができないのかもしれない。
もっとも、現在のわが家はまだ貸家住まいであり、いまだその目標は途上のままであるのだが。