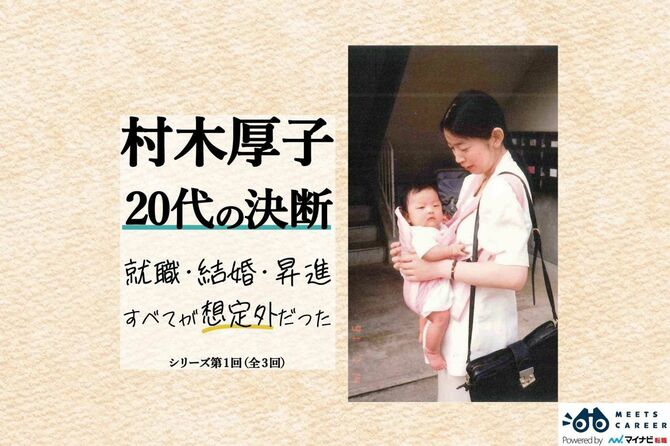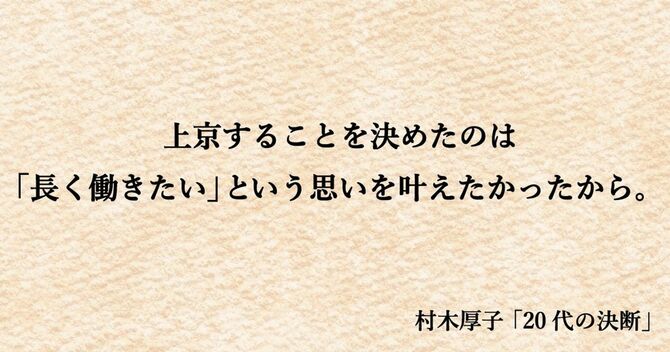人生は決断の連続。就職や転職、さらには結婚、子育てなど、さまざまな局面で選択を迫られます。時には深く悩み、逡巡することもあるでしょう。
充実したキャリア、人生を歩んでいるように見える先人たちも、かつては同じような岐路に立ち、悩みながら決断を下してきました。そこへ至るまでに、どんなプロセスがあったのでしょうか。また、その選択は、その後のキャリアにどんな影響を及ぼしたのでしょうか。
そんな「人生の決断」について、村木厚子さんが振り返ります。村木さんは1978年に労働省(現・厚生労働省)に入省して以来、女性政策や障がい者政策に携わり続け、国家公務員として37年間勤め上げました。女性が結婚・出産後も働き続けることが今ほど当たり前ではなかった時代にあって、「長く働き続ける」という目標を叶えるため、村木さんはどんな決断を下してきたのでしょうか。
1回目にフォーカスするのは、「20代の決断」です。
※全3回のシリーズの第1回です
「とにかく長く働きたい」という夢を叶えるために上京
20代最初の決断といえば、国家公務員になるために地元の高知から上京したことでしょうか。
私は中学から私立校に通い、途中で父が失業するなど経済的に苦しい時期がありながらも、大学まで卒業させてもらいました。「女子は大学に行かなくてもいい」と言われてしまうような時代でしたから、両親に対しては余計に感謝の気持ちが大きかった。同時に、ここまで教育を受けさせてもらえたからには、大学卒業後は自分の力で食べていける大人になろうと。「とにかく長く働くこと」が、社会に出るにあたって最初に抱いた夢でした。
ただ、私が就職活動をしていた1970年代後半は「男女雇用機会均等法(※1)」もなく、四年制大学を卒業した女性を雇ってくれる地元の民間企業はほとんどありませんでした。唯一、公務員だけは採用枠があり、“消去法”で受けたのが高知県庁の職員と国家公務員だったのです。幸い、どちらも合格しましたが、そうなると「地元に残って県庁に勤める」か、「上京して国家公務員になる」のか、大きな選択を迫られます。
※1……職場に生じている男女間の格差を是正し、男女の機会均等や待遇の確保を図ることなどを目的とした法律。1985年制定、翌86年施行。
東京はなんとなく怖いイメージがあったし、国家公務員が何をする仕事なのかもあまり分からない。それでも上京することを決めたのは、「長く働きたい」という思いを叶えたかったからです。今となっては想像しようもありませんが、当時の県庁は「男性職員の仕事」「女性職員の仕事」が明確に分かれていて、「企画は男性職員の仕事で、女性職員の仕事は“庶務”です」のようなことを言われた記憶もあります。女性という理由で“限られた仕事”しかさせてもらえないのではないか。国家公務員のほうが、まだ長く働ける可能性があるかもしれない。だったらそこに賭けてみよう、と。
そんな経緯で当時の労働省に入省し、私の公務員人生がスタートしました。20代のうちは能力が追いつかないながらも、やれることを懸命にやって、楽しく働くことができました。30代、40代、50代を振り返っても、仕事自体は男性と同じようにさせてもらいましたし、2015年に退官するまで37年にわたり勤め上げられたわけですから、あのときの決断は正しかったのだと思います。