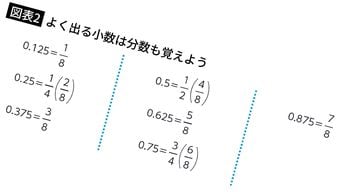※本稿は、小原雅博『外交とは何か』(中公新書)の一部を再編集したものです。
昭和の戦争との決定的違い
明治日本は帝国主義の時代にあって、国家独立の危機に直面する中、「富国強兵」を掲げ、外交と軍事がそれぞれの役割を発揮しつつ連携し調和し一体となって「坂の上の雲」をめざして駆け上がった。その結果が二つの戦争の勝利であった。成功要因は何と言っても外交と軍事の一元的管理による連動にあった。
それは戦争が政治の延長としてなされたことを意味する。出口戦略も用意されていた。すべてを指導層が総攬し、大局的で合理的な判断を下した。日清戦争では、政治・外交を預かる首相の伊藤(博文)と軍事を預かる第一軍司令官の山県(有朋)が緊密に連携した。文官の伊藤は大本営の会議にも列席した。議会も伊藤の戦争指導を全面的に支援した。日露戦争も同様である。開戦を決定した1904年1月12日の御前会議で奉呈された大山巌参謀総長の上奏文にある次の一文がそのことを明らかにしている。
《その(戦争)発動の機はもっぱら戦略上の利害にもとづき決定せられざるべからず。これ政略と戦略の合同一致すべき最大緊要の急務なり》
大山の発言は、当時の指導者たちが政治・外交と軍事の関係の重要性を深く認識していたことを示す。昭和の戦争との決定的な違いがここにある。
「明治モデル」は機能しなくなっていく
しかし、成功の物語を紡いだ明治モデルは日露戦争後、内外の変化によって次第に機能しなくなっていく。
本書で既に述べた通り、内では、明治の創業世代が一人また一人と去り、軍事と外交の総攬者たり得る第二世代の外政家が求められる一方で、閉鎖的な士官学校で純粋培養された少壮将校たちが台頭する。戦勝によって勢い付いた国民の民族主義的強硬論は外交を掣肘する。
外では、明治の時代が幕を閉じた翌々年、第一次世界大戦が勃発した。欧州での大戦によって列強のアジア関与は弱まった。日本は利権拡大の「千載一遇」のチャンスと捉えた。機会便乗主義の動きを主導したのが大隈重信内閣の加藤高明外相である。加藤が中国に突き付けた21カ条要求は中国の民族感情を大いに傷つけ、排日運動の原点となった。