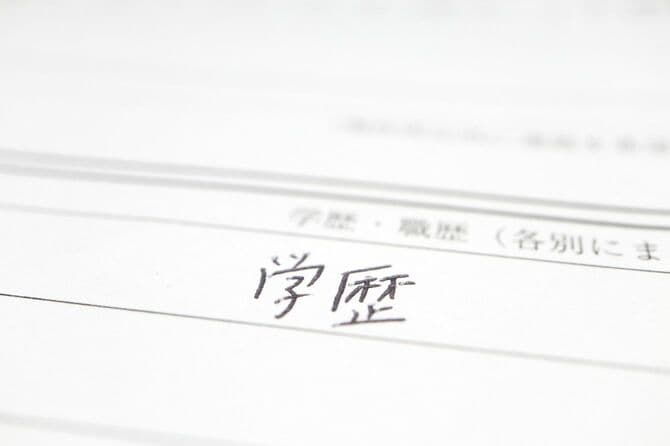※本稿は、ジェニファー・ウォレス『「ほどほど」にできない子どもたち 達成中毒』(早川書房)の一部を再編集したものです。
「よい」大学に入れば人生は安泰なのか
子どもを消耗させる風潮の根底には、よい人生は、「よい」大学に入学することで確保されるという確固たる信念が横たわっている。私が取材した生徒のほとんどが高校は目標のための手段に過ぎないと考えていた。名門大学に入ることが、金銭面の成功、社会的ステータス、幸福への鍵を握るとくり返し教えこまれているのだ。
もちろん大半のおとなは広い視野を備えているので、そんなことはないとわかっている。一流大学に入ったのに望みどおりの人生を歩んでいない人など山ほどいる。それほど優秀ではない大学に入ったけれども、想像していたよりもはるかによい人生を歩んでいる人も山ほどいる。
「大学ランキング」とは何か
また、この信念はごく一部の狭き門の大学が「よい」大学で、それ以外はちがうという前提に立っている。その前提に則って、USニューズ&ワールド・レポート誌は1983年から毎年アメリカの大学1500校のランク付けをおこなっている。
バロンズ誌やプリンストン・レビューと同様、このランキングも小規模のリベラルアートカレッジから研究の一大拠点となる総合大学までの個性豊かな大学を平らにならし、スコアというひとつの評価基準であらわしている。
例を挙げると、2022年のUSニューズ誌のランキングでは、スタンフォード大学が100点中96点、ミシガン大学が80点、ペンシルベニア州立大学が64点である。この数字を見ると、スタンフォード大学がペンシルベニア州立大学よりも「優れている」のは一目瞭然だ。こういったランキングが進学校に通う生徒のあいだで幅を利かすようになった。
ポール・タフは著書『The Inequality Machine: How College Divides Us』(格差製造工場──大学がいかに我々を分断するか)で、USニューズ誌のランキングを印刷して上位30校の下に線を引き、それ以外の大学を志望しないように娘に命じた父親の話を紹介している。
とはいえ、専門家が分析すると、どれだけ大目に見ても大学ランキングというものは当てにならないことがすぐさま判明する。「ランキングは質を客観的に評価しているように見えるかもしれない。複雑な計算式を使って自分たちの見解をもっともらしく載せているのだから」と〈チャレンジ・サクセス〉の共同創業者であり、スタンフォード大学教育大学院の上級講師であるデニース・ポープは、2018年の報告書において説得力のある論調で綴っている。