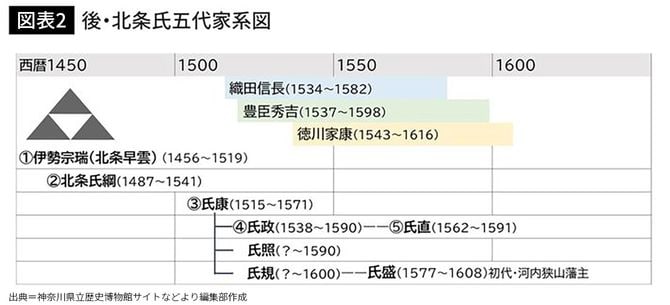氏康の父・氏綱は新興勢力・北条家の二代目で、狡猾な男
二代目当主の氏綱は、天文2年(1533)3月、鎌倉の鶴岡八幡宮を復興させて、関東に並びなき大名となる意欲を見せている。氏綱はわざわざ大和の興福寺から職人たちを呼び寄せて、大造営を開始した。関東にあるべき秩序を構築するには、その実力が必要だ。晴氏は、氏綱を主戦場に派遣する。
天文7年(1538)10月、氏綱は足利義明と国府台の地(現在の千葉県市川市)で戦って、見事にこれを討ち取った。決定打となったのは、氏綱自身の乗り込みである。苦戦に追い込まれた氏綱は、本陣を嫡男の氏康に預けると、自ら馬に跨って敵陣に突撃したのだ。
陣形を乱された小弓軍に、北条軍の猛攻が加わって、義明の敗死を招いたのである。総崩れが始まり、全ては誰もが認める決定的勝利に終わった。古河の晴氏は、氏綱を関東管領に任じて、その功績に報いた。
しかも晴氏は梁田晴助の妹(姉ともいう)を娶っていたが、氏綱の娘である芳春院殿(北条氏康の妹)を「御台(正妻)」に迎えた。晴氏と晴助妹との間にはすでに長男(後の足利藤氏)がいたが、芳春院殿もまた男子(後の足利義氏)を産んだ。
国府台合戦で義明を破った氏綱は、晴氏に重用されるが……
一連の流れは、晴氏と氏綱の君臣が幸せな結びつきを得たように思えるかもしれないが、当然ながら簗田晴助、上杉憲政らは面白くなかったはずだ。
それどころか、当の晴氏も実は不快に思うところがあったらしい。周囲の人間が大きく変わって、このままでは傀儡も同然ではないかと嘆きを強くしたのではないか。
そもそも氏綱はかなり狡猾な男であった。鶴岡八幡宮造営のときも、資金集めと称して房総に手のものを送り出し、親北条派と反北条派を明らかにしたあと、軍勢を送り込むなど、露骨な侵略計画を実行するほど計略に長けている。晴氏の囲い込みも、北条家の繁栄を考えてのことだろう。
とはいえ国府台合戦で晴氏のために命懸けの奮闘をしている辺り、単なる野心だけで公方の権力を奪おうとしたのではなく、晴氏の周囲からノイズを除去することが、公方のためになると考えていたようにも思える。
だが、その氏綱が亡くなると、足利晴氏は北条の影響力を排除しようと動き始めた。憲政や晴助もこの動きに加担する。天文11年(1542)、20歳の上杉憲政は、鹿島神社に「八州併呑」の野心をあらわす北条家と「決戦」して、「君」たる晴氏を助け、「民」を救いたいとの願文を捧げた。