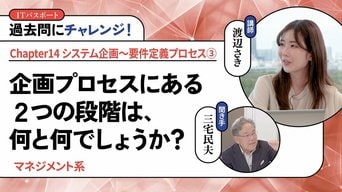9歳のとき家業が没落して、父母は失踪、離婚。まさに一家離散に直面した、苛烈な少年時代を過ごしながらも、後に老親の面倒は、最期までしっかりみたという。そこで学んだ教訓とは何か。浅田次郎、56歳。現代日本文学を代表する小説家が、自身の経験と願望を熱く語った――。
介護という言葉にはアメリカ的な義務感がつきまとっている
介護という言葉はあまり好きではない。子が親に孝行をつくすのは当たり前、ましてや家長たる男子にとって、それは明らかに人生の一部であるからだ。
本来、人間がやって当たり前のことに対して、なぜ特定の名称をつけるのか。最初にそういう疑問を感じたのは、シルバーシートがこの世に登場したときである。じいさんばあさんや赤ん坊を背負った人が来たら、立って席を譲るのは当然。疲れていても座席に座るのは格好良くない、恥であるという感覚があった。
自分が社会を背負っているという自覚さえあれば、そういうものだろう。ところがシルバーシートができたために、「そこでなければ席を立たなくていい」という逆説が生まれた。社会は弱者救済のために用意したつもりなのだろうけど、それがかえって麗しい習慣や儒教的モラルを破壊した。
シルバーシートの導入以降、日本社会では個人主義的なものの考え方が急速に広まった。介護やボランティアという行為自体はいいことだ。しかしながら、そういう言葉が必要な社会になってしまったのも事実だろうと感じる。孝の精神が欠落して、介護という社会的な用語を用意しなければならなくなったのだ。

浅田次郎●日本ペンクラブ専務理事 日本文藝家協会理事 1951年、東京都に生まれる。95年『地下鉄(メトロ)に乗って』で第16回吉川英治文学新人賞、97年『鉄道員(ぽっぽや)』で第117回直木賞、2000年『壬生義士伝』で第13回柴田錬三郎賞、06年『お腹召しませ』で第1回中央公論文芸賞、第10回司馬遼太郎賞、08年『中原の虹』で第42回吉川英治文学賞を受賞。近著に『月島慕情』『つばさよ つばさ』がある。
アメリカを旅するといつも思うのだが、あちらの老人は孤独だ。社会的なパワーを失った老人は社会から疎外される。アメリカでは「夫婦」が家族の単位だから、連れ合いに先立たれた老人の余生はひどくわびしい。パーティーは夫婦で呼ばれるのが基本だから、伴侶を失うとパーティーのお声がけもなくなる。
アメリカ社会には「家」の概念がない。子供たちは家を継ぐのではなく、結婚とともに独立して自分の家族と家庭を築く。たまに子供や孫が顔を見せにくるぐらいで、老人は必ず孤独になる。家の概念が多少なりとも残っている日本はまだ救われるが、それでも少しずつアメリカ社会と同じ方向に向かっているのではないだろうか。介護という言葉には、「すでに他人になった親の面倒をみる」というアメリカ的な義務感がつきまとっているように感じるのだ。