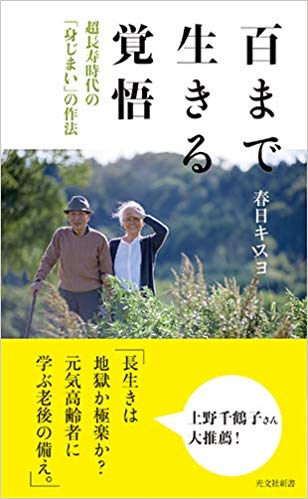※本稿は、春日キスヨ『百まで生きる覚悟』(光文社新書)の第5章を再編集したものです。
完璧すぎる「シングル高齢者」の死に支度
倒れた時のことは、「まだ考えていない」「成りゆき任せ」「誰かがどうにかするだろう」と言う人が多い中で、「うわー! すごい。老い支度、死に支度とは、若いうちからこういう形でしていくものなのか」と、驚き、学ばせてもらった2人の女性がいる。生涯シングルで生きてきた80歳のXさん、91歳のYさんである。
Xさんは、「私は結婚しないと決めた時から、老後に向かって生きていっているんで、早くから老い先のことを考えておかねばと考えて生きてきました」と語り、Yさんも、「私は一人ですから、倒れたら後は誰かに頼まなきゃいけないとずいぶん若い時から考えてました。真剣に取り組み始めたのは、母が亡くなった48歳からです」と語っていた。
しかし、身近に姉、甥、姪が住み、その助力を受けられるXさんと、5人姉妹の一番下で、存命の姉も年老いて、甥・姪も遠方に住み、その助力を受けられないYさんとは、「老い支度」「死に支度」のあり方も異なっていた。そこでまず、姉(85歳)、甥(62歳)、さらに姪(65歳)が、自宅から10分ほどの距離に住み、関係も良好なXさんが行ってきた「老い支度」「死に支度」から見ていこう。
30代から自分の最期を想定して物件を選んだ
ひとり暮らしの場合、「老い支度」として大事なのは、いよいよ弱った時、どこで誰と住むか、倒れた時、誰にまず発見してもらうかという問題が大きいが、Xさんの場合、48年間住み続ける現在の住居を33歳の時に選んだ時点で、すでにそのことを考えて物件を選んだのだという。
Xさん「今の借家に33歳から48年間住んでるんですが、借家にした理由は、自分で家を持つと、最後はそれを処分しないといけない。でも、家主がおれば最小限で済みます。それに、倒れた時に第一発見者がいないといけないと思って探しました。とにかく家主が身近にいれば、何かあっても相談できるじゃないですか。後始末も楽だし。鉄筋の家で、私は1階部分の半分。家主が2階です」
さらにXさんは、住まいとは別に、介護が必要になる将来に備え、53歳の時に、ある施設の一室の終身利用権も購入していた。
Xさん「53歳の時に確保したのは、病院が2階にあり、“歳をとって病気になればそこに入院可能”というのをうたい文句にした建物の1階部分の部屋でした。今は別荘にして、歳をとれば終の住処にしようと思って購入したんです。終身利用権だったから。でも購入から10年後、病院が撤退して、施設の性格がコロッと変わり、20年後の73歳で手離しましたが」