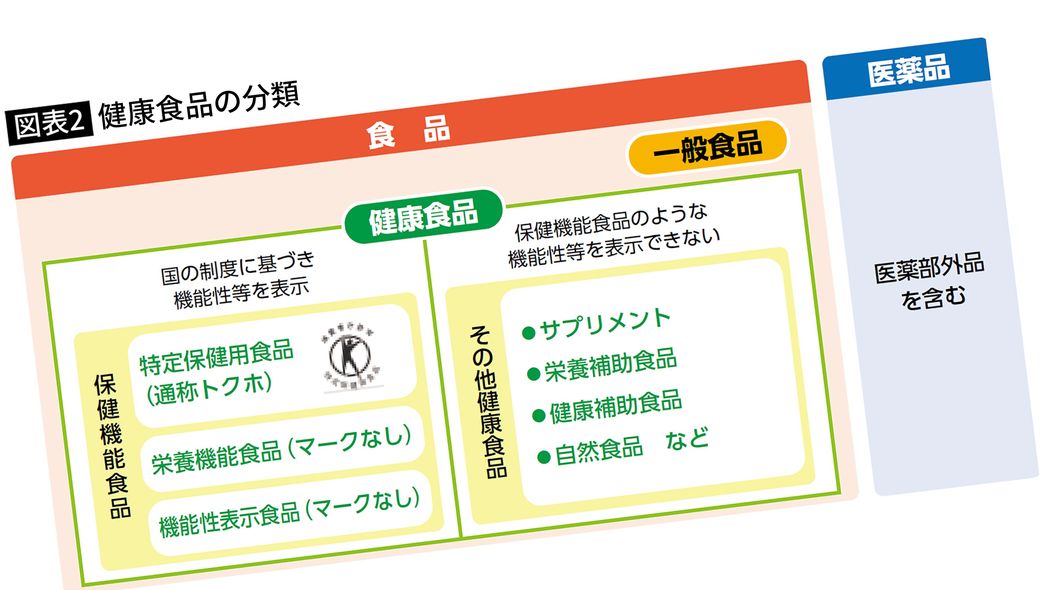小林製薬の紅麹サプリメント問題で「機能性表示食品」という制度に批判が集まっている。科学ジャーナリストの松永和紀さんは「健康食品業界にエビデンスという概念が定着したことは評価できる。しかし、お粗末なエビデンスで国民をだます製品が数多く存在していることは罪深い」という――。
「悪玉コレステロールを下げる」という売り文句
小林製薬の紅麹サプリメントによる健康被害問題はいまだ、原因がつかめないままです。同社が把握している健康被害は、延べ相談件数が12万1000件、医療機関を受診した人が1603人、入院した人278人、死者数5人に上り、1日に1000件程度の相談が寄せられる状況です(5月23日現在)。
紅麹サプリメントは機能性表示食品。消費者は、容器包装の「悪玉コレステロールを下げる」という機能性に惹きつけられました。人気の製品であったが故に被害が拡大したのは疑いようもなく、機能性表示食品制度への批判も高まっています。
消費者庁は3月末、「機能性表示食品を巡る検討会」を設置し、検討しました。とはいえこの制度、功罪両面ありました。今回は、制度を改めて検証します。
かつて販売されていた「トンデモ健康食品」
機能性表示食品制度の“功績”は、健康食品の事業者や報道機関に安全性や機能性の科学的根拠(エビデンス)という概念をきちんと浸透させた点にある、と私は思います。
健康食品業界は、大手から中小まで開発力も科学的な判断力も千差万別。昔はとんでもない事業者が多かった、というのが私の実感です。培養細胞・動物試験の結果や体験談をチラシなどに掲載し「健康食品」として販売するところが多くありました。ヒトが食べての試験による効果など検証されていないのに、効果ありとアピールするのです。
効果・効能をうたうのは、薬事法(現薬機法)違反にも問われかねないので、容器包装への表示や広告宣伝は表現を工夫する一方、口頭で「あの人はこれで治った」などとセールスします。書籍で効果効能を詳しく説明し、「この書籍で取り上げられた成分を含むこの製品は……」と売りつける「バイブル商法」など、売らんかなのテクニックもさまざまありました。