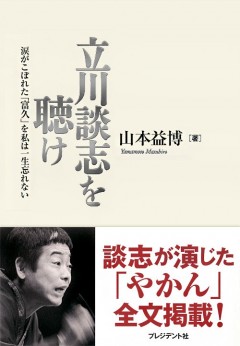1948年4月11日、東京都出身。早稲田大学第二文学部演劇学科卒。落語評論家、料理評論家。国立劇場小劇場の第五次落語研究会で桂文楽 (8代目)(黒門町)の落語を体験。大学の卒業論文はそのまま『桂文楽の世界』として商業出版される。この論文は現在でも桂文楽研究の最高峰。2013年には『名人芸の黄金時代桂文楽の世界』と改題されて、中公文庫より出版される。KTVの演芸番組「花王名人劇場」ではプロデューサーを務めていた。テレビ朝日「ザ・テレビ演芸」の「飛び出せ!笑いのニュースター」コーナーでは審査員としてダウンタウンらを審査。演芸、料理に関する著書多数。
【山本】まずはじめに言いたいんですけど、談志さんが亡くなってから突然みんなが神格化して、2、3年前ほとんど高座に上がらないころから、天才だ、神様だと言っているけど、ほんとにちゃんと聴いていたんですか? もっと丁寧に聴いてほしかった落語家なのに、なんていうか、きちんと聴いてない人が最後になって1回、2回聴いてそう言ってる人が多いんじゃないですか? というようなところをきちんと検証しなければと……。僕だって、大昔からそんなに聴いてるわけじゃありませんが、でも40年くらい前から聴いてましたから。
【元木】私は大学生のときからですから、半世紀近くになる。以前から松岡由雄さん(談志さんの弟)と談志さんの落語についての本をやるならぜひ山本さんに書いてほしいと話していた。今回この企画(立川談志を聴け)をやると松岡さんに話したら「ぜひ読みたいし、一つ聞いてほしいことがある」と。「途中、談志は十分聴いたと言って、談志を離れたのはいったいどういう理由だったのかということを聞いてほしい」と頼まれました。それはぜひ私も聞きたいと思ってます。
【山本】そこらへんも全部しゃべらないといけないですね。実をいうと、談志師匠が亡くなったとき新聞にたくさん弔辞が出たじゃないですか。でも、こんな弔辞じゃかわいそうだなというのが2つも3つもありました。はっきり言うと、朝日新聞の小三治師匠と、それから……、演芸評論家の矢野誠一さんの弔辞を読みました。私は、弔辞は、談志師匠のことを偲んだエピソードというか、人柄が出るようなことを書かないと申し訳ないなと思っていた。松岡さん(弟さん)もそう思ったらしいんですね。「どうして、新聞社が山本さんに弔辞を頼まないのかなァ」と。でも頼むわけないですよ。僕が落語をちゃんと現役で聴いてるというふうに新聞社の人は思っていないから。
【元木】すばらしい落語評論を書いていますが、しばらく時間が空いたということもあるけどね。
【山本】それで僕は自分のブログに“立川談志はこんな素敵な落語家だった”という話を弔辞のつもりで書いたらたくさんの人が読んでくださって、あぁ、そんなに心の優しい人だったのと。そういうところが、談志さんの素敵なところなんだけれど、実は表に向かって自分を表現してるのとまったく違う人だったんですよね。つまりテレビに出てなにか発言した結果、結局、テレビに出てる部分で判断をされて、談志師匠は誤解されていたフシが大いにありますね。
落語だけで勝負していてとても凄かったんですけど、落語だけの枠におさまらない。社会的現象じゃないけれども、テレビにまで出ていって誤解をされるというか……。自分に正直な人だったからそういうふうになってしまう。そういうところを、弔辞の中でそうじゃないよ、と書く人がいたらいいのになと思っていました。僕が書いた弔辞は、僕の個人的なエピソードなんですが、こういう落語を聴いたときに、こんな感じだったという落語の具体的な例をあげながら書いたんです。たとえば、「富久」の噺を書きました。「富久」をやったときに、終わったら談志師匠は高座の幕を下ろさせずに、自分を批評するじゃないですか。国立演芸場でのひとり会でしたけど、「非常にいい出来だった」と。ああ、久しぶりに「富久」のいいものを聴いたなと思ったら、談志師匠が最後に一言「今日は、久蔵に富が当たって本当によかったと思います」と言ったんです。えー? だって誰がやっても当たる噺ですよね!
【元木】富札を入れておいた大神宮さまのお宮が焼けてしまったと悲嘆に暮れる幇間の久蔵が、大神宮さまを運び出しておいたと鳶の頭に言われて狂喜する姿を演じて鬼気迫るものがありました。どうやっても当たるんですがね。
【山本】そういう噺ですよね? でも、談志師匠は「今日は久蔵に富が当たって本当によかったと思います」と言ったんです。ジーンときました。それで楽屋にまわって師匠に「なんで終わったあと、『今日は久蔵に千両富が当たって本当によかったと思います』って言ったんですか?」って聞いたら、「やってて出来がいいときは登場人物を操っている自分が後ろにいるんです」と。で、「今日の出来はやってる最中にあまりにも久蔵が悲惨な目に遇ってて、こいつにやっぱり、千両でも当てさせてあげたいなって気持ちに、後ろにいる自分が思ったんで、そういうふうに言った」と言うんですよ。
すごくいいときには、自分と登場人物がちゃんと二重構造で高座でやれてるんですって。それを聞いたときに、ただ高座で落語を聴いてるだけじゃなくて、ああ、落語とはそういうふうに冷めている芸能なんだな、と思いました。冷めていながら、すごく熱い思いが伝わってくるじゃないですか。「当てさせてあげたい」と言うけれど、だれが噺をやっても当たるのに、談志師匠はそういう熱い思いをもっていた落語家だったんじゃないかという例です。