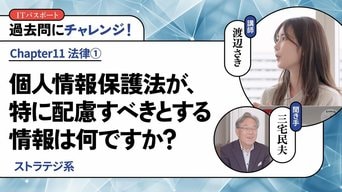償還時に元本割れが発生する恐れも
仕組み債は、主として①特定の国債や社債などの債券と、②特定の企業の株式やインデックスを原資産(アンダーライング・アセット)とする金融派生商品=デリバティブ、を組み合わせてつくられる。そのため仕組み債の目論見書などには、債券の発行者と、対象株式などの名称が記載されていることが多い。
近年のわが国における仕組み債の傾向として、相対的に利回りの高い債券と、オプション(決められた日、あるいは一定の期間内に対象となる資産を特定の価格で買ったり売ったりすることができる権利)を組み合わせて組成されたものが多い。
デリバティブを使っているため、金融市場が大きく変動すると想定外の損失に直面する恐れがある。また、仕組み債にはノックイン条項が設けられていることが多い。対象の株価などが、あらかじめ定めた水準(ノックイン価格)を下回ると仕組み債が利益を生むことなく早期に償還されたり、償還時に元本割れが発生したりする恐れがある。
なぜハイリスク投資に手を出す人が増えているのか
通常の国債など確定利付き証券の場合、年間に支払われる利息(インカムゲイン)が定められている。満期償還時には元本(100円)が支払われる。利率と満期があらかじめ決められた債券のキャッシュフローは予想しやすい。しかし、仕組み債のキャッシュフローはノックイン条項などに大きく影響される。仕組み債の保有からどの程度の利得が得られるかは、プロの投資家でも正確に予想することが困難だ。
それにもかかわらず仕組み債を購入する人が増えた。その一因として、わが国の超低金利環境が長期化したことは大きい。1990年代以降のわが国では、バブルの崩壊によって経済が長期の停滞に陥った。1999年には日銀が“ゼロ金利政策”を導入し、2001年には“量的緩和政策”が導入されて金融緩和策が強化された。その後、ゼロ金利と量的緩和策は一時解除された。リーマンショックを挟み、2013年4月以降は異次元の金融緩和が実施された。