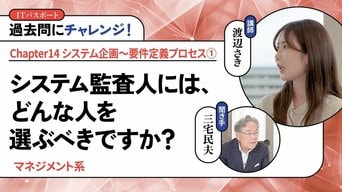「家族に見守られながら畳の上で死にたい」というのは、多くの日本人が抱く「死」への希望だろう。では、そうやって死んだ後、どのように葬られたいか。先祖代々の墓に入りたいのか、妻であれば夫と同じ墓か、親が眠る実家の墓か、はたまた樹木葬や散骨など、新しい選択肢を選ぶのか……。ライフスタイルの多様化によって、私たちは今、死後にまで至る終末期のライフデザインを迫られている。
「“先祖代々の墓”という考えが、そもそもの間違いのもと」と語るのは、第一生命経済研究所主任研究員であり、『変わるお葬式、消えるお墓』などの著書を持つ小谷みどりだ。
「『○○家之墓』と書かれた黒や灰色の墓石の下に、火葬した遺骨を骨壷に入れて納めるのが日本の伝統的な埋葬の形だ、と考えている人は多いと思います。しかし、墓石のあるお墓が庶民の間にも普及したのは江戸時代中期以降のことで、たった300年くらいの歴史しかありません。また、火葬が普及したのは、明治時代末期から大正時代にかけてのこと。それすら都市部を中心に起きた現象で、全国規模で完全に普及したといえるのは1960年代以降です。それらを踏まえると“先祖代々”とはいっても、今あるお墓に入っているみなさんの先祖は、せいぜい2~3代前まで。いってしまえば、伝統でもなんでもないんです」

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント