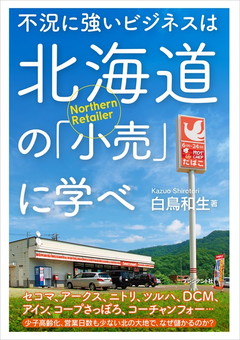ここで必要なのは、「農政」だけでも「商流」だけでもなく、両者をつなぐ“エコシステムとしての再設計”だ。
具体的には次のようなものだ。
・実態に即した需給統計の整備(家庭外食や総菜向けも含めた把握)
・用途別の品種設計と、そのインセンティブづくり
・備蓄米の品種・活用法の見直し(加工・業務用途も対応)
・物流費や加工費を含めた流通インフラへの政策的支援
小泉大臣「問屋叩き」に疑義あり
こうした取り組みのうえで、責任の所在をあいまいにしたまま“誰かを悪者にする”言説には、冷静に向き合いたい。
ディスカウントストア「ドン・キホーテ」を展開するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)が強調する「卸を通さず直接仕入れれば安くなる」という主張や、小泉農相の“問屋不要論”も、一見すると「正論」のように見える。
しかし現実には、全国に産地・集荷・精米・在庫・供給をネットワーク化し、緊急時の緩衝役を担っているのは、まさにその“見えない卸”の存在である。彼らなしには、安定供給も備蓄活用も回らない。
「卸が悪い」という単純な批判は、構造的な問題のスケープゴートをつくるだけだ。実際、卸は備蓄や需給調整において不可欠な役割を担っており、その役割を正しく理解すべきだ。必要なのは、対立ではなく仕組みのアップデートだ。
余っているかに見えるが足りない現実
コメが高い。買えない。手に入らない――。その背景には、気候変動や収量減だけでなく、制度疲労・物流制約・統計の不備・流通構造の断絶といった複合的な構造的要因がある。
「コメが余っていた時代」は終わった。いま私たちは、“余っているかに見える”コメと、“使えるコメが足りない”現実のギャップに直面している。
社員食堂の米の味が落ちた、コンビニのおにぎりの価格が妙に高くなった――そんな日常の変化の裏にあるのが、制度と現場の「ほころび」かもしれない。
令和5年産の主食用米の生産量は約690万トン、1人あたりの年間コメ消費量は約50.7キログラム(2023年度)。政府の備蓄米はおよそ100万トンとされているが、そのうち年間の売渡量(入れ替え分)は約20万トン前後にとどまり、市場への影響は限定的である。一方、家計調査(2024年)によれば、家庭用のコメへの支出は1世帯あたり年間2万7196円。これに対し、調理食品(総菜)への支出は年間15万5977円に達し、このうち弁当・おにぎりなど「主食的調理食品」(6万7317円)の比重が高まっている。つまり、「炊く」から「買って済ませる」へ食の外部化の流れは、統計上も明確に進行する。
コメは単なる主食ではない。生活の基盤であり、社会課題の鏡でもある。「令和のコメ騒動」は、そんな当たり前の価値を、あらためて私たちに問い直している。