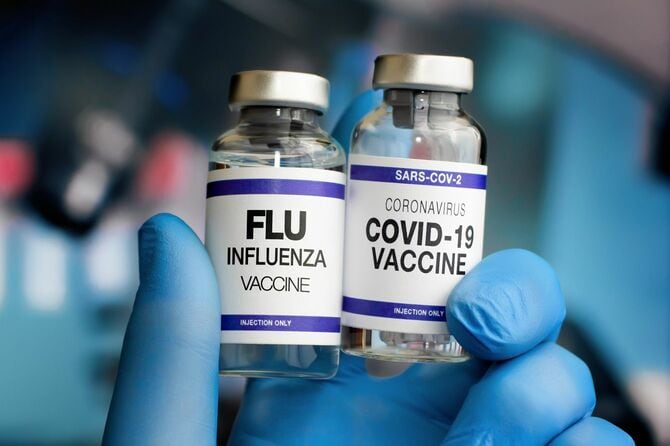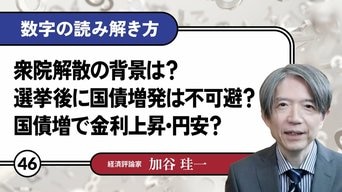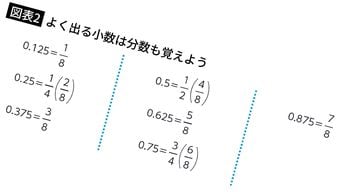※本稿は、竹内薫『フェイクニュース時代の科学リテラシー超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を再編集したものです。
科学は常にくつがえる可能性がある
科学とは何かを語るうえで、「反証可能性」という哲学的なキーワードを紹介しましょう。
これはカール・ポパーという人が提唱した概念で、科学と、科学でないものを区別する基準を示しています。
ポパーの提唱した内容はこうです。
それに対して、科学以外のものは反証が可能とは限らない。
科学においては「ある実験をした結果、ある理論が否定された、つまり反証が挙げられた」がつねに可能ということです。絶対に反証できない理論があったとしたら、それは科学ではないんです。
現代では、ほとんどの科学者がこの考え方に則って科学に取り組んでいます。
「100%正しい理論」なんて存在しない
誰でも知っているニュートン力学や、アインシュタインの一般相対性理論についても、当然ながら反証可能性はあります。少し前にも、素粒子の「標準理論」という現代科学の根底にある理論に対して、必ずしも正しくないのではないかと主張する論文が出ています。
理論上、「正しくないかもしれない」という可能性から始まって、「じゃあ実験してみよう」という人が出てきて、実験をした結果、もし反証ができるのであれば、その理論はくつがえされます。基準としては明確ですね。
つまり、反証可能性があるということは、100%正しい理論、絶対的な真実というものは原則として存在せず、科学の出す結論はつねに「仮説」であると言えるのです。
ちなみに、過去にはポパーの提唱する反証可能性に異を唱えた人もいました。科学哲学者の、ポール・ファイヤアーベントです。もともとは天文学や数学、音楽などを学んでいましたが、のちに科学哲学に転向し、科学に対してアナーキズムを提唱しました。
ざっくりいうと、科学はつねに反証可能性があるなんてことはなくて、もっとアナーキーなもの、何でもありなんだと言ったんですね。ただ、彼はものすごくおもしろい哲学者ですが、主流の考え方ではありません。