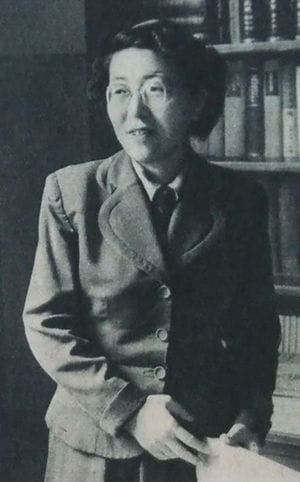生後70日の実子を殺害した29歳の女性を弁護した
「久米愛子(※原文ママ)弁護士は法服法冠の姿もうつり良く、堂々たる中にも淑やかさを備えた立派な態度で弁論に入った、落ち着きはらった頼もしい音声である」
記事は法廷でのやりとりを描写も交えて伝えている。彼女が述べた弁論も紹介されている。
「『人間として親子の情愛は最高のもの、ことさらに母親に於て一層深いものであります。実に母はその子の為には如何なるギセイも厭いません。その我が子を殺すに至った被告は実にやむにやまれぬ、どうにもせむ方つきての母子心中を選ぶ他なかったのであります』
水を打った如き法廷に、再度執行猶予の恩典を求める久米女史の切々胸を打つ弁論は終わった。深く頭を垂れた。被告の肩は細かにふるえて、ふっくらとした両頬に紅さしている」(法律新報627号)。
名調子の傍聴記で続きが気になるが、判決の記事は掲載されていない。被告人がどうなったのか、久米がどういう感想を抱いたのかは分からない。
会社員の夫は兵隊に取られ、2人の子を連れて岡山に疎開
彼女が法廷に立った昭和16年9月。夫の知孝は再び召集され、今度は満洲へ送られた。だがハルピンで肺炎にかかり、翌年帰国する。久米は幼い2人の子どもと夫の看病に追われた。昭和20年には岡山県津山に疎開した。夫は東京に残り、久米は2人の子どもを連れて岡山へ向かう。夫の知孝は、弁護士の佐賀千惠美の聞き取りにこう答えている。
「疎開した人間は、向こうから見たら、やっかい者です。愛はずいぶん気を遣ったようです。慣れないのに野良仕事を手伝いました。子どももまだ四歳と二歳だったので、子どもにも手がかかりました。愛は食べ物や着る物が悪くても、こたえなかったようです。むしろ疎開先に気兼ねして、精神的にまいっていましたね」(『華やぐ女たち女性法曹のあけぼの』)
帰京して間もない昭和21年には、4歳の長男を亡くす。戦後すぐのことで、医師の診察でも原因が分からないままだった。彼女にとっては、最もつらい時期であった。