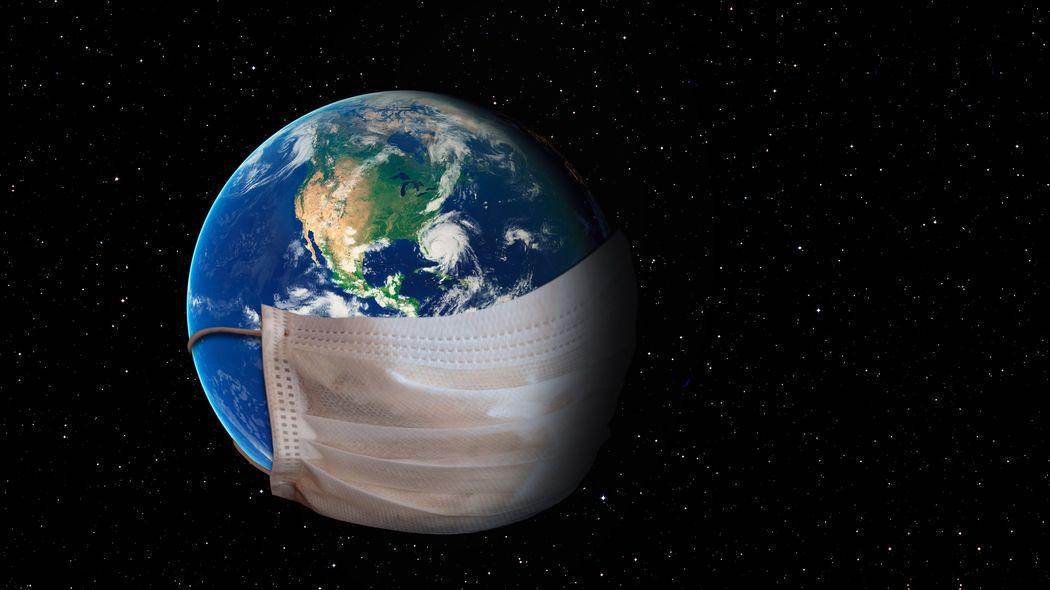※本稿は、池上彰・上田紀行・伊藤亜紗『とがったリーダーを育てる 東工大「リベラルアーツ教育」10年の軌跡』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
理系の学生にこそ「言葉で伝える」経験が必要
【上田】新型コロナウイルスの流行という未曾有の事態に、各国のリーダーはそれぞれ対応を迫られました。言葉の力で国民の共感を醸成した人がいたいっぽうで、はたして指導力を発揮できているのかと厳しい視線が向けられている人も見受けられます。いまこそリーダーの真価が問われていますが、その評価はさまざまです。
これからの時代のリーダー像を考える上で、これまでの議論をふまえ、意見交換の場を持つことが重要だと気がつきました。
【伊藤】本日はよろしくお願いします。私は池上さんが、「言葉の力」を理系の学生にこそ知ってもらいたいと書かれたことに注目しました。あらゆることを数式で表現しようとする東工大生に、「言葉で伝える」という経験が必要なのだと。そこに大切なことがあるように思います。
東工大では、新入生全員がスタートとなる科目が「立志プロジェクト」です。まさに、受験勉強に明け暮れた新1年生を入学直後に容赦なく言葉の世界に飛び込ませる科目だと思います。
そもそも「立志」とは聞きなれない言葉ですが、すごく面白い。「立志」とは、一見すると主語は「自分」で、「自分が志を立てるんだ」というふうに聞こえます。でも、実際に立志プロジェクトの授業を受けると、主語は決して自分ではないことに気がつきます。社会にとって必要なことは何か、人間のみならず生命界全体を考えたときにどうすべきか、数百年後の地球を考えたときにいま自分がすべきことは何かと、他者の視点から問うことが求められるからです。
リーダーたちが使った「戦争」というメタファー
【伊藤】そうすると、「立志」の主語は「自分」から、「自分ではないもの、自分のまわりの大きな世界」に替わる。この主語の転換は、学生らにとってインパクトは大きいようです。それまでどっぷりと漬かってきた受験という自己本位の発想から、周囲の世界に自分を向ける発想へと、視点の転換が行われる。「立志」には、じつはこんなスイッチが仕込まれているのだと、面白いなと思いました。
【池上】それは、自分中心ではない、新たな視点の獲得でもありますね。
【伊藤】はい。そんなところから、リーダーと言葉の力について考えてみました。いま私は、指導者たちがさまざまな場面で使うメタファーが気になっています。言葉の力というとき、このメタファーの力は大きく、重要だと思うのです。
たとえば今回の新型コロナで、リーダーたちが使ったメタファーでもっとも頻繁に聞こえてきたのは「戦争」という言葉でした。「これはコロナとの戦争である」と。そこから戦略を立て、戦術を考え、コントロールしていこうとする。そんなリーダーが多かったのですが、そのメタファーは正しかったのか。そもそも新型コロナウイルスとは、人類が戦うべき敵なのかということです。