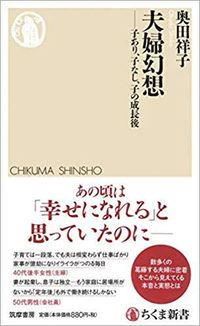夫の協力のもと、時短をとらず働いた
男児2人を出産し、それぞれ育児休業を取得して就業を継続した。管理部門から、入社時から希望していた広報に異動するなど、着実にキャリアを積み重ねていった。
当時、出産後に職場復帰した女性が出世とは縁遠いキャリアコースに固定されてしまうことを指す「マミートラック」という言葉はまだ登場していなかったが、現実問題として、育児との両立で仕事の量が減るのに伴って質も落ち、働くモチベーションが低下する女性は多く、それが離職要因にもなっていた。彼女の場合は、そうした状況に陥らないように、職場復帰から一定期間だけ残業を免除してもらいながらも、短時間勤務は希望せず、できるだけ周囲と同程度の仕事量をこなせるよう努力していたようだ。
そうして、それを実現できたのは、商社勤務の夫が保育園の送り迎えや家事の分担などを協力していたからで、夫への感謝の気持ちを幾度となく口にしていたのが印象的だった。
第2子を出産して数カ月過ぎた2010年、東京都心にある職場近くの喫茶店で仕事帰りに取材に応じてくれた佐野さんは、仕事や育児の疲れを微塵も見せることなく、はつらつとした表情だった。平日の終業後の時間を指定され、保育園の迎えなど子どもの世話に支障はないのか尋ねたのだが、残業時など帰宅が遅くなる時は、夫が子どもの面倒を見てくれているということだった。
夫の育児協力に一抹の不安
「私も夫も地方出身なので、近くにいて育児を協力してくれる親、きょうだいはいません。だから、夫が子育てや家事を手伝ってくれていて、とても助かっているんです。それに、夫は有能で仕事でも次々と実績を上げていますし、尊敬しています。大学で同じゼミだったんですが、今は夫婦であり、同志のような関係でもあります。ただ、夫には職場のパワーゲームを勝ち進んでもらいたいと願っているので、育児協力が負担となって仕事に悪影響がないか、実は心配でもあるんです」
「でも、ご主人は自分から協力してくださっているようですし、仕事に支障が出ているとは、おっしゃっていないんですよね」
「そうですね。時々尋ねても、『大丈夫だよ』って言ってくれます。私の取り越し苦労だといいんですけど……」
この時、佐野さんが抱いていた一抹の不安がやがて、現実のものとなることを取材者である私はもとより、彼女自身も予測していなかったのではないだろうか。
(後編に続く)
写真=iStock.com
京都生まれ。1994年、米・ニューヨーク大学文理大学院修士課程修了後、新聞社入社。ジャーナリスト。博士(政策・メディア)。日本文藝家協会会員。専門はジェンダー論、労働・福祉政策、メディア論。新聞記者時代から独自に取材、調査研究を始め、2017年から現職。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科博士課程単位取得退学。著書に『捨てられる男たち』(SB新書)、『社会的うつ うつ病休職者はなぜ増加しているのか』(晃洋書房)、『「女性活躍」に翻弄される人びと』(光文社新書)、『男が心配』(PHP新書)、『シン・男がつらいよ』(朝日新書)、『等身大の定年後 お金・働き方・生きがい』(光文社新書)などがある。