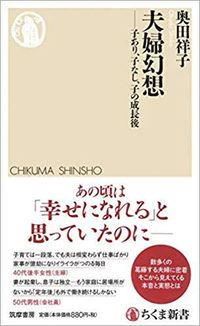※本稿は奥田祥子『夫婦幻想』(ちくま新書)の一部を再編集したものです

「幻想」という呪縛
共働き世帯が専業主婦世帯を上回ってから20年余り。女性は家庭と仕事を両立させて当たり前という風潮が広まり、さらに2016年に施行された女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)を契機に、管理職に就いて能力を発揮する「活躍」妻が注目を集める時代を迎えている。一方、男性も家庭を顧みない仕事人間はネガティブなイメージで捉えられ、子育てに積極的に関わる「イクメン」が新たな夫像としてもてはやされている。
しかしながら、現実はどうなのか。家事・育児をこなしながら管理職に昇進し、世間が求める女性のライフスタイルを実現したかに見える女性の中には、夫との関係で苦悩を抱えているケースが少なくない。良き夫を目指すあまりに男のプライドとのジレンマに苛まれている男性も多い。行く手には「マミートラック」や「パタニティ・ハラスメント」など、自力ではどうすることもできない厚い壁が立ちはだかる。
社会から期待された女性、男性になろうとすればするほど、最も身近で親密な関係であるはずの夫婦の溝が深まる。そして、自身の理想とかけ離れていく夫・妻の姿に絶望した揚げ句、「幻想」に陥り、その呪縛から抜け出せなくなってしまうのである。
なぜ、「幻想」の中にしか夫婦を描けなくなってしまうのか。ここでは夫婦ともに仕事と家庭を両立させ、「活躍」妻と「イクメン」夫を目指す事例を通して考えてみたい。
「生気を失った」夫に絶望する妻
「結婚、出産後も仕事を辞めず、子育て、家事と両立させながら、管理職にまでなって……社会から求められている女性を目指して、これまで一生懸命に頑張り、欲しいものはすべて手に入れたつもりだったのに……実際には違ったんですね。課長になってからというもの、夫とは全く会話がありません。以前はあんなに前向きで仕事もデキて、生き生きとしていた夫だったのに、今ではすっかり変わって生気を失ってしまって……もう夫には絶望しました」
2017年、神奈川県の閑静な住宅街にある自宅で、当時43歳の佐野(さの)敦子さん(仮名)は苦渋の表情で思いの丈をぶつけ、嗚咽した。長年の取材で、彼女がここまで激しい感情を露にしたのは初めてだった。
この数年前から、もしかすると関係が思わしくないのかもしれないと感じるようになり、本人が自発的に語ってくれるのを待っていた状況ではあった。だがここまで深刻化し、苦悩しているとは思いもよらなかった。
そんな両親の不和を察したのか、小学生の子どもたち2人は、食事以外では自室にこもった切りで、話しかけても必要最低限の短い言葉しか返ってこないのだという。
女性活躍の模範的なライフスタイルだったのに
佐野さんは、時代の潮流でもある「女性活躍」の模範ともいえるライフスタイルを実現した女性だ。
2013年に第2次安倍内閣が成長戦略のひとつに「女性が輝く日本」を掲げ、2016年には、従業員300人以上の企業など雇用主に女性管理職の数値目標などを盛り込んだ行動計画の策定と公表を義務づけた女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が施行された(300人未満の雇用主は努力義務)。こうした流れを背景に、企業などの女性登用の動きは一気に加速している。行動計画は管理職登用に限定したものではないが、メディアを介して社会に浸透していく過程において、女性の管理職比率を増やすことが「女性活躍」政策であるとミスリードされていった面も否めない。その結果、「子育てと両立させながら働いて、さらに管理職に就く」という女性の生き方の規範を押しつけることにもなってしまったのである。
このような生き方の規範については、プレッシャーを感じたり、抵抗感を抱いたりする女性が少なくない。そんななか、佐野さんは自ら進んで「女性活躍」のライフスタイルを実現したのだ。
彼女は実は、もとから上昇志向が強かったわけではない。
「無理せず仕事も家庭も」が理想
東北出身で東京の難関私立大学を卒業後、メーカーに総合職として入社した佐野さんとの出会いは、2005年にまで遡る。当時、31歳で半年ほど前に結婚したばかりの彼女に、仕事と家庭の両立などこれからの人生をどう歩んでいきたいと考えているのか、インタビューしたのだ。
「今、『負け犬』か、『勝ち組』か、なんて、世の中で話題になっていますけれど、女の人生を勝ち負けに分けるなんて、ばかげていると思いませんか? 女性が結婚か仕事かの二択に迫られていた時代に逆戻りしたみたいじゃないですか。奥田さんとかの世代。あっ、いえ、すみません」
「全然、構いませんよ。気にしないで、率直な意見を話してくださいね。じゃあ、仕事も家庭も両方をこなしていきたい、と考えているのですか?」
「ええ、もちろんです。会社の両立支援策だって整いつつあるし、利用できる制度は社員の権利として使えばいいと思います。それに、夫も子どもができたら育児協力してくれると言ってくれていますし。別に目尻をつり上げて仕事も家庭も、と意気込む必要はないと思うんです。まあ、実際にそういう女性の先輩がいるから、そうはなりたくないなあ、って。私たち団塊の子ども世代は、受験も就職も競争相手が多くて厳しかったから、高望みしない、欲張らないくせがついてしまっているのかもしれません。仕事は続けるけれど、男の人と同じような働き方だと家庭と両立させていくのは難しいから、出世していくキャリアコースではなくて、肩の力を抜いて無理なく働いていくのがいいですね」
ブームに惑わされず、両立していく
佐野さんは歯に衣着せぬ物言いで、自然体で明るく、率直な考えを述べてくれた。当時の取材ノートには、発言や表情などの記述のほかに、「気負いなく、いい」「これからの女性はしなやかで、強く!」などと、彼女の言動に対する私自身の思いが何か所か記されていた。自分よりも10歳近く年下の佐野さんのような女性が、新たな時代の女性のライフスタイルを実現してみせてくれるのではないか。期待のような感情を抱いたことを、昨日のことのように思い出す。
ちなみに、彼女の語りに登場した「負け犬」とは、2003年初版の書籍『負け犬の遠吠え』(酒井順子著)で描かれた、30歳代以上の未婚で子どものいない女性のことで、論争とともにブームを巻き起こした。「負け犬」のカウンターパートである、結婚していて子どものいる「勝ち組」(同著では「勝ち犬」と称されたが、論争・ブームでは多くで「勝ち組」が使われた)は、センセーショナルなメディア報道も相まって、経済的にゆとりある生活を送る専業主婦へと拡大解釈、誤読されて広がった。そして、女性の社会進出に逆行するかのように、専業主婦を志向する女性がじわじわと増えていることを当時、私は取材を通して実感していた。
このようなブームに惑わされることなく、佐野さんは仕事と家庭を両立させ、そして出産、子育てを経験していくのだ。
夫の協力のもと、時短をとらず働いた
男児2人を出産し、それぞれ育児休業を取得して就業を継続した。管理部門から、入社時から希望していた広報に異動するなど、着実にキャリアを積み重ねていった。
当時、出産後に職場復帰した女性が出世とは縁遠いキャリアコースに固定されてしまうことを指す「マミートラック」という言葉はまだ登場していなかったが、現実問題として、育児との両立で仕事の量が減るのに伴って質も落ち、働くモチベーションが低下する女性は多く、それが離職要因にもなっていた。彼女の場合は、そうした状況に陥らないように、職場復帰から一定期間だけ残業を免除してもらいながらも、短時間勤務は希望せず、できるだけ周囲と同程度の仕事量をこなせるよう努力していたようだ。
そうして、それを実現できたのは、商社勤務の夫が保育園の送り迎えや家事の分担などを協力していたからで、夫への感謝の気持ちを幾度となく口にしていたのが印象的だった。
第2子を出産して数カ月過ぎた2010年、東京都心にある職場近くの喫茶店で仕事帰りに取材に応じてくれた佐野さんは、仕事や育児の疲れを微塵も見せることなく、はつらつとした表情だった。平日の終業後の時間を指定され、保育園の迎えなど子どもの世話に支障はないのか尋ねたのだが、残業時など帰宅が遅くなる時は、夫が子どもの面倒を見てくれているということだった。
夫の育児協力に一抹の不安
「私も夫も地方出身なので、近くにいて育児を協力してくれる親、きょうだいはいません。だから、夫が子育てや家事を手伝ってくれていて、とても助かっているんです。それに、夫は有能で仕事でも次々と実績を上げていますし、尊敬しています。大学で同じゼミだったんですが、今は夫婦であり、同志のような関係でもあります。ただ、夫には職場のパワーゲームを勝ち進んでもらいたいと願っているので、育児協力が負担となって仕事に悪影響がないか、実は心配でもあるんです」
「でも、ご主人は自分から協力してくださっているようですし、仕事に支障が出ているとは、おっしゃっていないんですよね」
「そうですね。時々尋ねても、『大丈夫だよ』って言ってくれます。私の取り越し苦労だといいんですけど……」
この時、佐野さんが抱いていた一抹の不安がやがて、現実のものとなることを取材者である私はもとより、彼女自身も予測していなかったのではないだろうか。
(後編に続く)