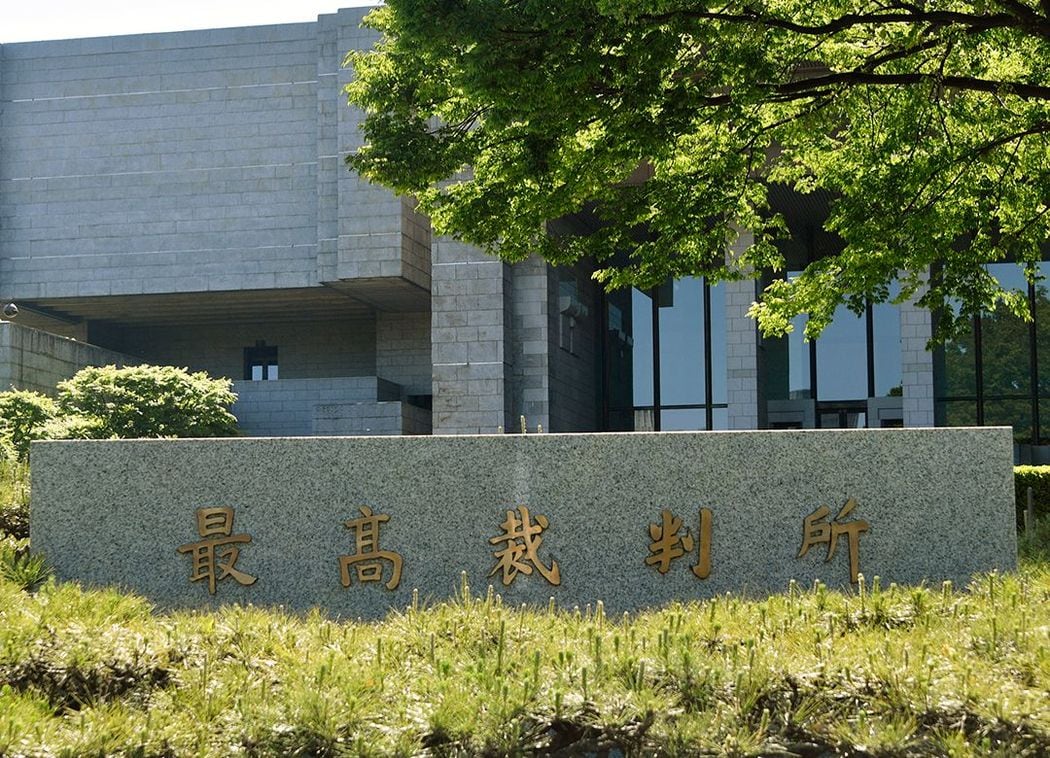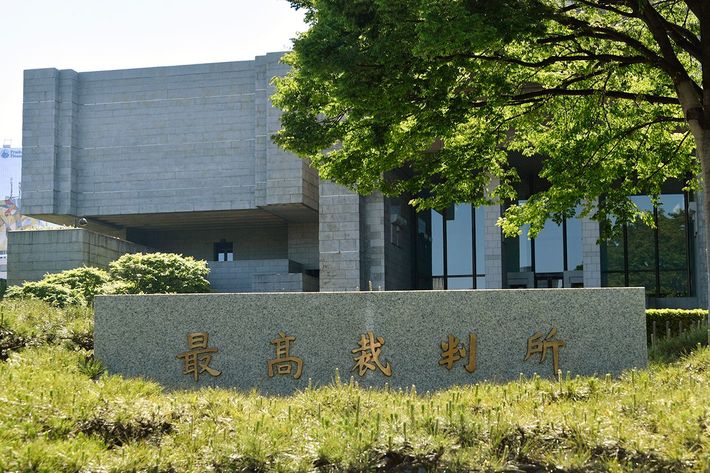40代男性が「共同親権」を求めて最高裁へ
2018年10月、東京都内の40代男性が共同親権を求めて最高裁に上告したことが話題になった。離婚後の単独親権は、「家」制度の名残で憲法違反だという主張である。「家」制度のない欧米諸外国も、かつては単独親権であったから、「家」制度の名残とはいえないであろう。
だが、そんな欧米諸国も、近年は非嫡出子を含めた共同親権に道を開いている。また、日本でも2014年から批准の効力が発生している「ハーグ子奪取条約」は、片親が子を連れて国境を越えて逃げた場合、もとの居住国に戻すことを命じており、締約国が当事者の自力救済を封じることを原則としている。
日本国内でも、片親が子を連れて逃げる事態を減らすために、「共同養育支援法(旧:親子断絶防止法)」が超党派の議員連盟から提唱されている。たしかに夫婦としては失敗した2人でも、両親として子の育児に協力できるのであれば、もちろんそのほうが望ましいだろう。それでは、これらの主張のように、両親の仲が悪くなった場合でも、両親が共同に親権を行使できるように法改正すべきだろうか。
家族への「公的な介入」が少ない日本は特殊
この問題を考えるためには、日本家族法の特徴を理解しなくてはならない。151年前に成立した明治政府は、日本語になかった「権利」「義務」「時効」という法律用語の翻訳語をつくるところから始めて、主にドイツ民法とフランス民法に倣った「明治民法」を30年かけて立法した。しかし家族法の部分は、モデルになった母法と日本法との間に、大きな相違がある。
明治民法の起草者たちは、西欧法は、離婚をすべて裁判離婚とするなど、手間のかかる不要な国家介入が多すぎると判断した。そこで、戸籍の記載を単位に「家」制度を作り、「家」の自治にすべてを委ねる、極端に私的自治を重視した独自の家族法を立法したのである。
届出のみで成立する協議離婚は、この日本家族法の特徴を代表する制度である。「家」制度を廃止した戦後の民法改正は、この極端な「家」の私的自治をそのまま家族当事者の私的自治にスライドさせた。その結果、日本家族法は、比較法的には、家族への公的介入が著しく少ない特殊な立法となっている。
戦後改正の基準となった日本国憲法は、自由と平等を機械的に要求するだけであって、「合意」を至上とする家族法の欠陥を是正する力を持たなかった。形式的な自由と平等は、他人間の関係においては基準となるルールであったとしても、家族間には妥当しない。
家族内部は、実際には決して平等ではなく、意思すら抑圧する力関係の差があり、当事者の相互依存は極めて強く、離脱することは容易ではない。法による弱者の保護がなければ、実質的な平等が保たれないどころか、悲惨な抑圧や収奪も生じうる。家族当事者の協議に委ねることは、一見、家族の自由を認めるように見えるが、実際には家族のむき出しの力関係のなかに家族内の弱者を放置することになる。