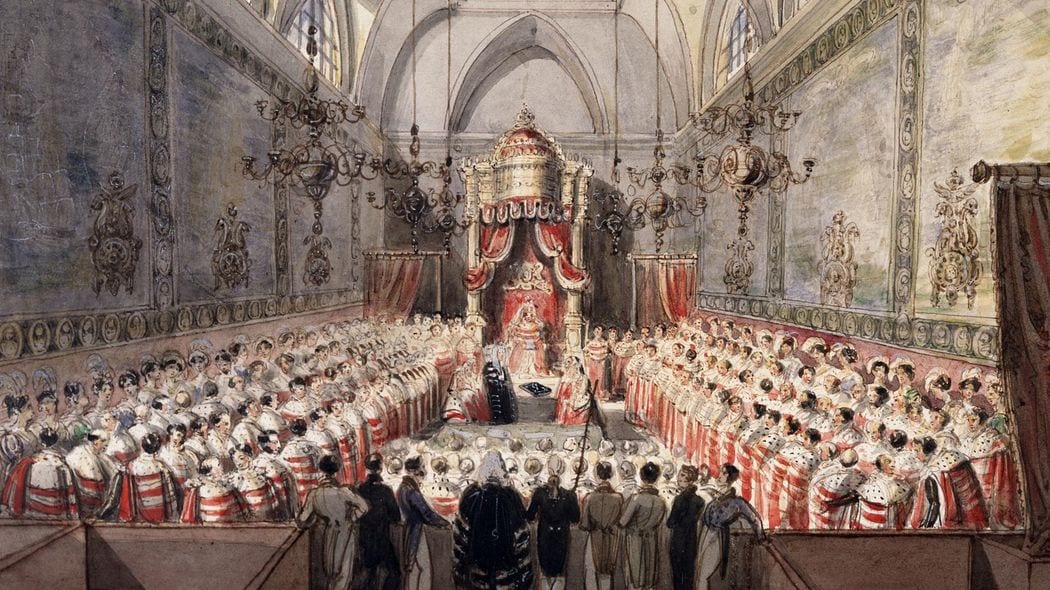※本稿は、君塚直隆『教養としてのイギリス貴族入門』(新潮新書)の一部を再編集したものです。
他国と比べて大金持ちだったイギリス貴族
イギリスに限らず、ヨーロッパが貴族政治によって支配されていた19世紀。大陸には大勢の貴族たちが跋扈していた。プロイセン(ドイツ帝国の中核を担った)には2万人、イタリアには1万2000人、オーストリアには9000人の貴族がおり、ロシアにいたっては100万人以上の貴族がひしめいていたとされている。
当時のロシアの人口(約1億2500万人)と比較しても、その数は多すぎた。もし19世紀末のロシアと同じ人口比の貴族がイギリスにいたとしたら、その数は30万人以上にも達する。
ところが、当時のイギリスには爵位貴族は580人、准男爵(バロネット)も856人という具合に、貴族の数は人口のなかでもきわめて少ない比率しか占めていなかったのである。それにもかかわらず、彼ら爵位貴族だけで国土の実に半分ほどの土地を占有していたのであるから、イギリス貴族はヨーロッパの貴族たちと比べても桁違いの大金持ちであった。
イギリス貴族にもおとずれた「たそがれどき」
しかし、そのイギリス貴族にもついに「たそがれどき」がおとずれることになる。まずは1870年代から本格化した「農業不況」である。
アメリカ南北戦争(1861~65年)が終結するや、交通手段の急速な発達により、南北アメリカ大陸やオセアニアから大量の安い穀物がヨーロッパ大陸へと流れてきた。それはロシア、プロイセン、フランスの地主階級に大打撃を与えるとともに、イギリスにもその余波は及んだ。
さらに、19世紀末からジェントルマン階級に襲いかかってきたのが、不動産を対象とする「相続税」であった。
それまでは、動産を対象とする相続税はあったものの、不動産はお目こぼしにあずかっていた。それが1894年の自由党政権の政策により、100万ポンド以上の価値をもつ土地を所有する地主には8%の相続税が課せられるようになったのである。このときでさえ、特に保守党系の貴族らが牛耳る貴族院では大きな反発の声があがったが、20世紀に入るやこの税率はさらに高まっていく。