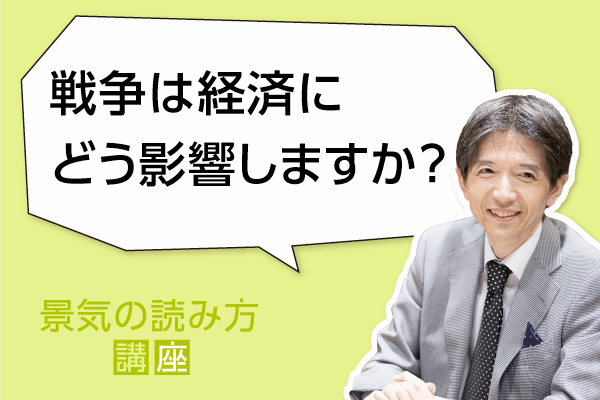
国内ではバブル以来の株高や大企業の賃上げが話題になる一方、米トランプ政権が打ち出す通商政策が景気の懸念材料になるといわれます。ニュースをにぎわす経済現象は身近な景気にどう結びつくのでしょうか。経済評論家の加谷珪一さんが、経済の不思議をやさしく読み解きます。第8回のテーマは、《戦争の経済効果》です。
物資不足、インフレ……当事国経済にもたらす悪影響
長く続いたロシアによるウクライナ侵攻ですが、国際社会が望まなかった形とはいえ、停戦の方向性が見えてきました。今回の戦争では原油価格や小麦価格が上昇するなど、全世界に悪影響が及んだほか、激しい戦闘が行われたウクライナ国内では、経済活動が大幅に制約された状態が続いていました。停戦が実現すれば、今後の復興にもある程度見通しがつくと期待されます。
一般的に戦争が行われると、戦闘による人的・物的被害や物資の窮乏といった事態が発生しますから、経済にはマイナスの影響が及びます。一方で、戦争特需などという言葉もあり、景気浮揚効果が見込めるといった話をする人もいます。実際のところ、戦争は経済に対してどのような影響を及ぼすのでしょうか。
戦争が経済に与える影響については、どこで戦争が行われるのかによって大きく変わってきます。今回、激しい戦闘が続いたウクライナ国内では主要な農産物の一つである小麦の生産が滞ったり、日常的な経済活動が抑制されたりするなど、経済は壊滅的な状況にまで追い込まれました。一方、ロシア側も、戦争が長引いたことで相当な予算を戦争につぎ込む結果となり、物資の不足やインフレ(物価上昇)など悪影響が及んでいます。
基本的に戦争の当事国は、何らかの形で国内経済に悪影響が及びますから、戦争が経済を良くするという効果はほとんどありません。一方、戦闘と直接関係なく、戦争当事者と貿易上の取引がある国は話が変わってきます。
朝鮮戦争、第一次大戦で日本が享受した「戦争特需」とは?
今回のウクライナ侵攻では、米国はウクライナに対して多額の武器援助を行いました。お金の出所は税金ということになりますが、武器を製造している企業からすると一気に注文が増える形になりますから、業績が大幅に拡大したところも少なくありません。今回の戦争によって、米国の一部企業が大きな利益を得たというのは事実であり、米国経済にはそれなりにプラスの影響を与えていると考えて差し支えありません(ここではこうした形で企業業績が拡大することの倫理的な是非は一旦、横に置いておきます)。
戦争によって日本経済に景気浮揚効果がもたらされたケースとしては、戦後、間もなく発生した朝鮮戦争があげられます。
日本は太平洋戦争の敗北によって、ほぼゼロの状態から経済をスタートしなければなりませんでした。ゼロになってしまった経済を復興させるのは容易なことではなく、本来であれば、日本は今でも貧しい国だった可能性が濃厚です。ところが1950年に朝鮮半島において朝鮮戦争が勃発し、日本は米軍の供給基地としての役割が期待されました。結果として日本企業には、さばき切れないほどの注文が殺到し、日本経済は奇跡的に成長軌道に乗ることができました。もし朝鮮戦争がなければ、今の日本経済はなかったと断言してよいでしょう。
日本の歴史についていえば、大正時代に発生した第一次世界大戦も似たような効果をもたらしました。
日本は直接戦争に参加しなかったことに加え、戦地となったヨーロッパから物資の注文が相次ぎ、日本経済は空前の好景気となりました。株式市場はバブルとなり、近年でいえば1980年代のバブル経済に似た状況になったことが知られています。
国家予算の280倍!……日本を破滅させた太平洋戦争の巨額戦費
一方で、自身が当事者だった戦争は結果次第では国家を破滅させかねない事態を招きます。日本が大敗北を喫した太平洋戦争は世界史的に見ても最悪の戦争の一つだったといえるでしょう。
日本は太平洋戦争(日中戦争含む)に国家予算の280倍(インフレ修正前)という途方もない金額を費やし、一連の戦費のほぼ全てを、日銀による国債直接引き受けで賄いました。これによって日本は凄まじいインフレとなり、終戦後、消費者物価指数は約200倍にまで高騰。預金は価値をなくし、多くの日本人が全財産を失ってしまいました。
このように、戦争というのは状況次第では国家を破滅に追い込む可能性がありますから、戦争によって経済を拡大させるという考え方は基本的に正しくありません。
軍事支出に他産業への波及効果は期待できるか?
ここまでひどい状況にならなくても、戦争を遂行する場合には装備に多額の支出を行うことになりますが、兵器の製造や開発にかかる支出というのは、他産業への波及効果が高くありません。したがって、経済学でいうところの乗数効果(投資や政府支出などの経済活動が全体に波及して、最終的には何倍もの効果を生み出す仕組み)は働きにくいと考えてよいでしょう。海外から装備品を調達した場合には、そのお金は全て海外に流れてしまいますから、GDP(国内総生産)の計算上は純粋なマイナスとなります。
全世界的に見ると、各国のGDPと軍事費にはある程度の相関関係があり、約2%が平均値といわれます。この数字がさらに上昇し5%を超えてくると、経済に後ろ向きの力が働いてきます。
ちなみに日本は防衛費をGDPの1%以内に抑えることを政府目標としてきましたが、米国の要請を受け、これを2%に拡大する方針を決定しました。2%は世界的に見て平均的な水準であり、経済的にはまったく問題ありませんが(あくまで経済的な問題に限定して言及しています)、この水準を大きく超えて金額が増えてくる場合には、経済活動への悪影響について考慮する必要があるかもしれません。
軍事費「5%超」でもロシア経済は壊滅しない!
今回、ロシアは戦争を遂行したことによって2023年には軍事費がGDPの5%を超過しました。経済に悪影響を及ぼし始めるレベルの支出ですが、5%程度の支出であれば、戦争継続そのものに問題は生じません。戦争が始まった当初、多くの専門家がロシア経済は壊滅すると主張していましたが、筆者などごく一部の専門家だけがロシアは戦争継続が可能と分析していました。
筆者はロシアを支持するつもりはまったくありませんし、今回のロシアの行動は国際社会として厳しく対処する必要があると考えています。しかしながら、数字というのはウソをつかないというのも厳然たる事実です。冷静にデータから分析すれば、ロシアに戦争継続が可能であることはハッキリしており、日本はその現実を前提に外交を展開する必要があったはずです。今回の出来事は、相手国の状況を想像や願望で分析することほど恐ろしいことはないという現実を、まざまざと見せつけたといってよいでしょう。
近年は世界経済のグローバル化が進み、ある地域の産業動向が世界経済にも大きな影響を及ぼすようになっています。規模の大きい戦争が発生するとグローバルなサプライチェーンに影響が及び、最終的には物価高騰や物資の不足といった事態が発生することになります。こうした時代においては、国際協調を高め、可能な限り紛争を止めていく努力が必要となります。ウクライナでの戦争がどのような形で終結するのかは、今後のグローバル経済のあり方を考える上で、重要な分岐点となるでしょう。
