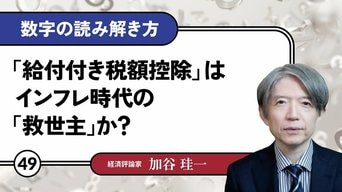※本稿は、三砂慶明編『本屋という仕事』(世界思想社)の一部を再編集したものです。
本に囲まれる生活は幸せだが、結局は「売れてなんぼ」
斜陽産業といわれる書店業界で働く人の多くは「本好き」がその理由だろう。かく言う私もそうであり、さらに独占禁止法の例外規定である再販売価格維持制度により、どこで買っても同じ価格の「本」を少しでも安く購入したいという不純な動機もあった。
実際に書店に立ってみると自分が好きな本など、巨大な本の海の中ではそのほんの一部でしかないことに気付く。殆どの本は何の興味も湧かないものなのだ。それでも本に囲まれ、本を触って一日の大半を過ごすことは気分の良いものである。
しかし書店は営利事業であり、本は商品である。自分の好きな本を並べて悦に入りたければ自らの部屋の本棚ですればよく、書店の本は「売ってなんぼ」「売れてなんぼ」なのである。
棚を背にする書店員と、棚に向かう書店員
書店の最も大事な商売道具は棚である。書店員には2つのタイプがあるという。棚を背にして仕事をする者と、棚に向かって仕事をする者である。どちらも棚に何を揃えるかには熱心だが、前者はその品揃えをバックに直接読者(顧客)や著者に働きかけることを好み、後者は棚を通して来店客に自らの思いを伝えようとする。
丸善&ジュンク堂書店梅田店の福嶋聡などが前者の好例であり、私は人見知りのため後者であらざるを得なかった。後者の方が言葉で伝えられない分、棚づくりにはこだわりが強くなりがちである。
私がジュンク堂書店に入社したのは同社が店舗を拡大してゆく前で、入社1年後に同社が専門書を重視するきっかけとなった専門書専門店サンパル店(当時)が開店し、その法経書(同社では社会科学という)担当として初めて棚を持った。
私自身の専門は日本中世史であり、法経書など縁もゆかりもなかったが、以後丸10年白紙の状態から法経書を売り続けることで、専門書を売るということについて自覚的になったように思う。その後転勤や人文書への異動を繰り返しながら、退職するまで大型店の専門書担当であり続けた。以下はあくまでもその立場からの棚論である。