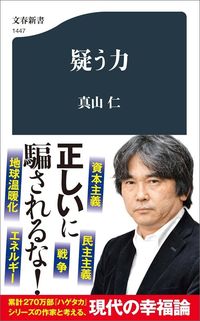減点主義が日本社会をダメにした
どんなことでも、自分でやらないと本物の力になりません。それなのに、やらせて見守るということができなくなっているのは、なぜでしょうか。
大きな理由として、減点主義がはびこっていることが挙げられます。企業の場合に、それが顕著です。企業が成熟するにつれて、かつての創業社長にはあった度量の大きさを持つ経営者がいなくなってしまった。今の経営者は、減点主義の中で失敗をしなかった人が多い。だから、部下に対しても同じことを求めます。
そんな中では、「やりたいようにやれ、骨は拾ってやるから」というようなセリフは絶対に出てこない。
失敗は恥ずかしいことで、マイナス評価につながると刷り込まれたら、誰も挑戦なんてしようとは思わなくなるでしょう。
しかし、挑戦のないところには成功も成長もありません。
成功のためには挑戦が必要で、挑戦すると失敗もする。挑戦して失敗するのは当然。上に立つものは、揺るぎなくそう伝え続けるべきです。
それが今できない理由は、日本社会の現状や経済状況にあるのかもしれません。
ですが、社会のせいにしてあきらめるのではなく、現場で「どんどんやれ、失敗してもいい」と若者に挑戦させるのは、課長レベルでも、先輩レベルでもできるはずです。まずはここから始めるという覚悟が求められています。
成功は、挑戦と失敗を繰り返した先にある
多様性を認めるとか、個性の時代だとか言いながら、多くの人は十把一絡に、たとえば「二十三歳はこういうものだ」と決めつけがちです。
同じ二十三歳にもいろんなタイプがあって、言われたことだけやる人もいれば、自分から動くのが好きな人もいる。できそうな人にはどんどんやらせればいいのに、なぜか一様に同じことをやらせようとする。そして、一つ失敗すると、全部失敗だと決めつける。
リーダーが考えるべきは、全員を成功させることではありません。組織としては、成功する人が、一人いればいい。今日はAさんが成功した、次に成功するのはC君かもしれない。その都度成功しそうな人に、その機会を与えればいい。組織の成功というのは、そういうものです。
本来、上に立つ人は目利きでなければなりません。個人の能力を見極めて、適切な課題を与える。自分でやらせる。失敗させる。挑戦して失敗するという面白さや楽しさをわからせる。
成功は、そのくり返しの先にあるものです。