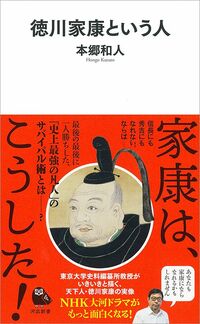信康と築山殿をかばわなかった忠次は家康に恨まれたか
信長は驚いて、忠次に「これは本当か」と尋ねた。そこで忠次が信康や築山殿をかばって「いや、それは違います。これも違います。信康様は間違っていません。築山殿も信長様を裏切っていません」というようなことを申し立てるのかと思いきや、ぜんぜん言い訳をしなかったのですね。「ああ、そういうこともありますね。それもありますね」というように答えた。
結局、結果として信康切腹という事態を招くことになりました。これが昔から語られてきた説です。家康にしてみれば「忠次の奴が少しでも説明をしてくれたら信康は死なずに済んだのに」と思うわけで、忠次を激しく憎んだ。
しかしそうした説に対して、最近の歴史研究者の中には「いや、そのあとも酒井忠次は家康に重く用いられているので、憎まれてなどはいなかった」という人もいます。たしかに信康切腹以降も、忠次は家康勢のリーダーとして扱われています。たとえば信長が死んだあとに、家康は信濃に攻め込んでいますが、そのときの指揮官は酒井忠次。こうしたところを見て「もし家康と酒井忠次の関係がよくなければ、そんな扱いはしないでしょう」という意見を出している。

与えられた領地、禄高を見ると明らかに差をつけられている
しかしそうした見立ては、司馬遼太郎に比べてはるかに浅いと思います。司馬遼太郎は『覇王の家』という小説で、信康切腹後も忠次が重く用いられていることをもって、それでも我慢したのが家康だ、家康はそこで我慢しなくてはいけなかったとして、三河武士団と家康の緊張関係を描いている。そうした考察の深さと比べて、先ほどの歴史研究者の解釈は、明らかに及ばないなというのが私の判断になります。
先に述べたように家康が関東へ移ったときに酒井家は四万石。四天王のうち井伊、榊原、本多は二桁。ほかに二桁の家はほぼない。だいたい二万石や一万石。それで忠次が家康のもとに「うちは家来の中で筆頭じゃないですか。それがなんでうちの倅(息子)は四万石しかもらえないんですか。もうちょっと増やしてやってくださいよ」とお願いに行った。家康はその忠次に「お前でも息子は可愛いのか」と応えたという逸話があります。
この話はどこまで本当なのかわかりません。「酒井忠次と家康は別に仲が悪くなかった」という人は「そのような逸話はなかった。ただの物語です」といいます。しかしその後を調べてみると、驚くことに、酒井は四万石に抑えられたままなのです。家康が関ヶ原の後で天下をとっても、酒井家は石高をぜんぜん増やしてもらっていないのです。