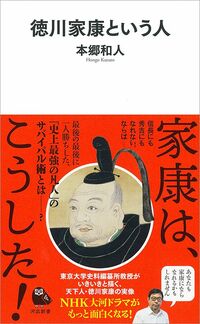※本稿は、本郷和人『徳川家康という人』(河出新書)の一部を再編集したものです。
徳川家臣団に激震が走ったナンバー2・石川数正の出奔
家康とその家臣の関係を考える上で忘れてはならない事件は「石川数正の出奔」です。石川数正は酒井忠次と並んで、徳川家康を支える二本柱のひとつのような存在でした。ただし筆頭はやはり酒井。序列的には石川はそれに次ぐ。
たとえば松平のルーツは安祥で、家康のお祖父さんの代から岡崎が本拠地。この安祥と岡崎は、三河の中でも「西三河」という地域になります。仮にもし、三河を松平家が支配していた歴史があったとしても、その勢力範囲は西三河であって、東三河には及んでいなかった。だから家康にしてみると、三河全体を統一するためには、まず東三河をがっちり支配する必要があった。その東三河の武士たちを束ねていたのが酒井です。いっぽうホームグラウンドの西三河の武士たちを束ねる役目が、石川ということだったらしい。
数正は自らの身を犠牲にして家康のスパイとなったのか
新しい領地と古い領地。どちらを任されるほうが、重要な任務だったか。それは当然、新しく家来になった人たちを束ねるほうが難しい。だから東三河は筆頭ポジションの酒井忠次が任された。そして西三河は、家来ナンバー2の石川数正が任されて束ねていました。
その家来ナンバー2の石川数正が豊臣秀吉のもとに出奔するという事件が起きたわけです。出奔したのはもちろん秀吉が天下人になった後ですが、この事件について小説家の山岡荘八は、自らの身を犠牲にしてスパイになりに行ったのだ、だから石川数正は実は大変すごい人なのだといったように書いています。しかしそうしたややこしい見解は、正直、歴史小説家として司馬遼太郎の深さには及ばないなと感じます。

というのも、当時の秀吉は各大名家の有力家臣をしきりにヘッドハンティングして、召し抱えようとしていたのです。
たとえば伊達政宗の伊達家に仕えていた、大河ドラマ『独眼竜政宗』でいかりや長介が演じた左月斎、鬼庭良直の息子を召し抱えたいという意向を見せましたが、鬼庭は「けっこうです」と断って伊達家に留まった。
伊達政宗の家臣や直江兼続もスカウトしていた秀吉
一番有名なケースは直江山城守ですね。上杉家の重臣である直江兼続に「俺の家来になれ」と誘ったが、直江もまた「上杉の家来でけっこうです」ということで秀吉の誘いを断った。成功した例だと島津家家老の伊集院忠棟。忠棟は秀吉直属の大名として日向庄内を領しています。秀吉はこのような感じで引き抜きを試みているのです。
ひとつは人たらしの秀吉のことですから「お前のところのこいつ、有能だよな。ぜひうちにくれ」という感じで単純に「有能な人が欲しいから誘った」という理由も、もちろんあったと思います。しかしもうひとつには、有力な家臣は当然その家の重要機密を握っている。それを引き抜くことで、その家のデータを取ろうとした意図もあったのではないでしょうか。いざ引っこ抜いてしまったあとはわりと冷淡で、手厚く遇するということは案外ない。そうしたところを見るとやはり、情報を取ることが目的だったのかなと思います。
石川数正はこうした秀吉の誘いに乗った。家康より秀吉を選択した。それだけのことで、自分を犠牲にしてあえてスパイになったなどと、極端な理解をすることはない。やはり三河武士であっても、好条件を提示されたらそちらに行くということがある。それだけのことです。
単純に数正は秀吉が好条件を出したから誘いに乗った
石川は信濃の松本の城主になります。ただ、これもまた家康の我慢強いところですが、関ヶ原のあと、豊臣から天下を奪った段階で石川を潰しにかかるかというと、それはやらない。当時はすでに数正の息子の代になっていましたが、「数正にもいいたいことはあったのだろうし、奴なりの理屈もあったんだろう」という感じで、潰さないでそのままにしておく。

家康という人は信長や秀吉のようには抜擢人事をやらない。信長は浪人出身の明智光秀を軍団長にまで引き上げましたし、そもそも木下藤吉郎時代の秀吉を起用している。その秀吉も大抜擢人事をやります。一番代表的な例は加藤清正です。加藤清正は「賤ヶ岳の戦い」で七本槍のひとりとして活躍し、その功で一躍三千石をもらう。それだけでもすごいのですが、その後、三千石からなんと二十数万石の大名に抜擢されます。「こいつは才能がある」と見込んだ人にはものすごい大抜擢をするわけです。
家康は、彼らのような人事はやらない。ですが昔ながらの世襲の考え方もあまりしておらず、「古くから松平の家来の家だから」と重く用いるようなことは案外やっていないのです。実際には、信長や秀吉に倣って、自分の目で見て「こいつは使えるな」と評価した人をしっかりと育てている。
家康は意外と実力主義の人事で報酬もベースアップした
もともと家康はケチなのでどーんと気前よく領土をあげることはあまりないのですが、とりあえず自分のまわりで使って三千石増やしました、五千石増やしました、それからまた一万石増やしました、という形で少しずつ少しずつ上げていく。そうした堅実なところは家康らしいといえます。
しかしそれでも人事の基本は能力。その人の能力を家康が認めるか認めないか、その人ができるかできないかで決める。だから家康と家臣の関係は、三河武士団がよそと違って特別に忠誠心があつかったわけではないし、主人もまた格別に厚遇していたわけでもない。後世に広まった「精強無比で忠実なる三河武士がいた」といった伝説は、ますます嘘くさい話だなとなります。

もうひとりの重臣・酒井忠次が冷遇されていたのはなぜか
二本柱のもうひとりは、酒井忠次。酒井氏は昔からの松平の家来で、忠次は家康の叔母さんの旦那。なので、血はつながっていないですが父方の叔父さんにあたります。この忠次が家来の筆頭第一号。しかし、実は酒井家は関東移転にあたって、四万石しかもらっていないのです。それはなぜかという話になります。
四万石でも、そこがものすごく大事な土地であればわかるのです。しかし酒井家に与えられたのは上総国の臼井というところで、別に要衝でも何でもない辺鄙な地域です。いったいなぜなんだ? と思ったときに、誰がいい出したのかわからないほど昔からいわれてきた説として、家康の嫡男・信康の切腹事件との関連が出てくることになります。
酒井忠次は、なかなかできる奴だった。織田信長は才能を愛する人なので、忠次も信長の信任を得ていた。だからこそ家康と信長の間の外交官みたいな役割も任せられていたのでしょう。その忠次が、信長の娘であり信康に嫁いだ五徳姫に十二カ条の不満を綴った手紙を持たされて信長のもとにやって来た。もちろん当時の手紙ですから、家来が中を見ることはできません。それを「預かってきました」と渡してみたら、中にはなんと旦那の悪口がいっぱい書いてあったわけです。
その中に信長がとても見過ごすことのできない内容がありました。「私を嫁いびりする姑の築山殿は武田とつながっています」という一条があったのです。
信康と築山殿をかばわなかった忠次は家康に恨まれたか
信長は驚いて、忠次に「これは本当か」と尋ねた。そこで忠次が信康や築山殿をかばって「いや、それは違います。これも違います。信康様は間違っていません。築山殿も信長様を裏切っていません」というようなことを申し立てるのかと思いきや、ぜんぜん言い訳をしなかったのですね。「ああ、そういうこともありますね。それもありますね」というように答えた。
結局、結果として信康切腹という事態を招くことになりました。これが昔から語られてきた説です。家康にしてみれば「忠次の奴が少しでも説明をしてくれたら信康は死なずに済んだのに」と思うわけで、忠次を激しく憎んだ。
しかしそうした説に対して、最近の歴史研究者の中には「いや、そのあとも酒井忠次は家康に重く用いられているので、憎まれてなどはいなかった」という人もいます。たしかに信康切腹以降も、忠次は家康勢のリーダーとして扱われています。たとえば信長が死んだあとに、家康は信濃に攻め込んでいますが、そのときの指揮官は酒井忠次。こうしたところを見て「もし家康と酒井忠次の関係がよくなければ、そんな扱いはしないでしょう」という意見を出している。

与えられた領地、禄高を見ると明らかに差をつけられている
しかしそうした見立ては、司馬遼太郎に比べてはるかに浅いと思います。司馬遼太郎は『覇王の家』という小説で、信康切腹後も忠次が重く用いられていることをもって、それでも我慢したのが家康だ、家康はそこで我慢しなくてはいけなかったとして、三河武士団と家康の緊張関係を描いている。そうした考察の深さと比べて、先ほどの歴史研究者の解釈は、明らかに及ばないなというのが私の判断になります。
先に述べたように家康が関東へ移ったときに酒井家は四万石。四天王のうち井伊、榊原、本多は二桁。ほかに二桁の家はほぼない。だいたい二万石や一万石。それで忠次が家康のもとに「うちは家来の中で筆頭じゃないですか。それがなんでうちの倅(息子)は四万石しかもらえないんですか。もうちょっと増やしてやってくださいよ」とお願いに行った。家康はその忠次に「お前でも息子は可愛いのか」と応えたという逸話があります。
この話はどこまで本当なのかわかりません。「酒井忠次と家康は別に仲が悪くなかった」という人は「そのような逸話はなかった。ただの物語です」といいます。しかしその後を調べてみると、驚くことに、酒井は四万石に抑えられたままなのです。家康が関ヶ原の後で天下をとっても、酒井家は石高をぜんぜん増やしてもらっていないのです。
たとえ恨んでいる部下でも我慢して活用した家康
酒井家は譜代大名の中でもトップのはず。これはどう見ても、家康が酒井を嫌いだったとしか見えない。そして、どうしてそこまで酒井のことを嫌っていたのかというと、やっぱり信康腹切事件が一番の原因ではないだろうか。しかしそうはいっても、家康が信長や秀吉と違うのは、信長の場合は「こいつは嫌いだな」となったらすぐ排除するでしょう? 秀吉もそこは似たようなものです。
しかし家康は我慢をする。小説『覇王の家』ではないですが、家康はその感情を表には出さずグッと堪えていた。「ちくしょう、この野郎、いつか見ていろよ」と思いながら家来の筆頭ポジションの酒井を相変わらず重い立場で用いた。
それが関東へ行くときになってようやく「もうそこまですることはないな」ということで酒井家を「叔母さん(臼井殿)がまだ生きているから、まあ四万石はやるけど、本当は四万石もやりたくないね」という扱いにした。そうした印象を受けます。領地の増やし方を見ると、家康は「俺の目の黒いうちは酒井を許さん」と考えていたようにしか見えない。
家康存命中は干されていた酒井家は秀忠の時代に出世
結局、どうなるかというと、家康が死んだのち、秀忠が徳川の実権を完全に手にしたとたんに酒井は一発で十万石に増やしてもらいます。さらに庄内で十四万石をもらい、ここで飛び抜けて増えて、酒井十四万石というと、譜代大名の中で井伊に次ぐ石高となる。秀忠にしてみると、信康が生きていれば自分は将軍になれなかったということもありますし、家臣全体のことを考えて、「冷遇はもういいんじゃないか。領地を増やしてあげるよ」ということだったのではないでしょうか。
そうすると、酒井家の石高が家康存命中には抑えられていた理由は、信康の一件しかないのではないか。それが今のところの私の考えです。最近つくづく思うのですが、昔から唱えられている定説って、唱えられるだけの根拠というものがあるのですね。いっぽう、自分が目立ちたいからと、とにかく昔からいわれてきたことをひっくり返してみても、全体的なバランスから見るとやっぱり昔の説でいいじゃないかということがしばしばあります。新しけりゃいいってもんじゃないし、奇抜なことをいえば勝ちということはない。最近すごくそう思います。「司馬遼太郎の考察は深かった。やっぱり偉大だな」と、あらためて感じます。