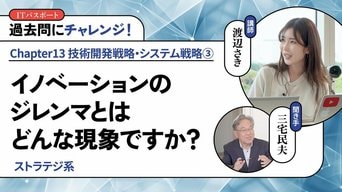都市部の電車は、朝晩の通勤・帰宅時間帯に大混雑する。この通勤ラッシュ、昭和時代はどうだったのか。ノンフィクションライター・葛城明彦さんの著書『不適切な昭和』(中公新書ラクレ)より、一部を紹介する――。
乗れなかった客は「自分が悪い」
昭和50年頃までは、東京23区内などでも整列乗車はほとんど行われていなかった。ホームでもサラリーマンらはただ適当に並んでいるだけ。電車も停車位置が毎日微妙に違ったりするため、目の前にドア部分が停まると、「今日はラッキー」などといっていたのである。また当時は、「降りる人が先」などというルールもなかったため、押し戻されて下車しそこなう人もたくさんいた。
ラッシュ時の乗車などはまさに弱肉強食の世界。力の強い男性が最優先で乗れることになっており、女性や子供、障害者などがはじき出されることも多かった。通勤時間帯には誰もが「俺さえ乗れれば」と思っており、みなが1つのドアに向かって突進する姿は、さながら芥川龍之介の『蜘蛛の糸』のようであった。
しかし、駅や鉄道会社に苦情や意見をいう人などはおらず、乗車しそこなっても、「弱かった自分が悪い」として自身を責めているケースが大半だった。
毎朝「尻押し部隊」が大奮闘
電車も今と違って短い編成のものが多く、輸送力が低かったため、都内では「乗車率300%」などという状態も普通だった(よく「酷電」などとも呼ばれた)。駅ではドアのそばで客を押し込む「尻押し」がよくなされていて、学生のアルバイトも大量動員されていた。
窓ガラスが割れることもしばしばあったが、応急処置としてセロテープで貼り付けただけで、どの鉄道会社もそのまま運行させていたのだから、凄い時代である。