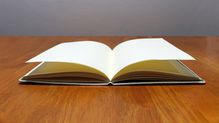住友銀行は他社と人事交流がない「独立王国」だった
当たり前ではあるが、化学科卒は住友化学工業に多く、電気科は住友電気工業、機械科は住友金属工業が多い。これらに対し、住友鉱業には採鉱冶金科がいない。住友財閥は三井・三菱に比べて鉱山経営の規模が小さかった。採鉱冶金科の学生にとって、同社の魅力が低かったのだろう。
一方、東京大学文系であるが、住友銀行(22人)、住友信託(12人)、および住友本社(18人)が圧倒的に多く、この3社で全体の3分の2(65.8%)を占めている。住友信託は1925年に設立された比較的若い企業で、銀行からの転籍が多いと想定される。住友銀行は他社と人事交流がない「独立王国」であるから、東京大学文系の多くは住友銀行(+住友信託)に振り分けられたと考えるべきであろう。

ここから先は無料会員限定です。
無料会員登録で今すぐ全文が読めます。
- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信
- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能
- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能
- 記事をブックマーク可能