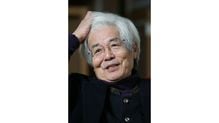※本稿は、中野剛志『入門 シュンペーター』(PHP新書)の一部を再編集したものです。

ほとんど知られていないシュンペーターの貨幣論
ジョセフ・シュンペーターの『経済発展の理論』は、イノベーションを「新結合」として理論化したり、イノベーションの担い手としての「企業者」の概念を提示したりしたことで、よく知られています。
その一方で、シュンペーターが『経済発展の理論』の中で、貨幣について極めて重要な議論を行なっていることについては、シュンペーターの専門家以外には、ほとんど知られていません。
しかしながら、シュンペーターの経済発展やイノベーションの理論は、彼の貨幣についての議論を踏まえておかなければ、本当に理解したことにはならないのです。そこで、今回は、『経済発展の理論』における貨幣論について、簡潔に解説し、その現代的な意義について議論したいと思います。
まず、シュンペーターは、経済の類型を「静態的」と「動態的」に分けました。「静態的」な経済は、消費と生産、需要と供給が一致し、均衡・安定している状態を維持している経済です。
「静態的」な経済において、貨幣は、支払手段や交換価値の尺度として使われています。このため、貨幣は、商品の流れとは反対方向に流れています。
「静態的」な経済では、完全な競争の結果、企業の収入と支出(機会費用を含む)の差額である「純利潤」(経済学上の利潤)はゼロになっています。また、需要と供給が均衡しているので、そもそも、消費のために使う量以上に貨幣を貯蓄しておく必要性に乏しいという特徴もあります。
完全な競争状態なら企業に純利潤は存在しない
さて、ある企業者Aが、手織機しかなかった「静態的」な経済において、力織機の導入という「新結合」(既存の物や力をまったく新しい形で組み合わせること。シュンペーターが考えるイノベーションの本質)を行なおうとしたとします。
この場合、企業者Aは、力織機を開発するにせよ購入するにせよ、資金を必要とします。しかし、その資金をどこから調達してくるのでしょうか。企業者Aは、自らの貯蓄から資金を捻出するか、あるいは他の貯蓄を有する企業者から資金を調達してくるのだろう。そう思われるかもしれません。
しかし、「静態的」な経済では、企業には「純利潤」というものがありません。言い換えれば、市場が均衡している状態の経済に存在するのは、利益がわずかしかない中小零細企業ばかりだということです。ということは、新結合を行なうのに必要な資金を捻出できるほどの貯蓄というものは、どこにも存在しないはずです。