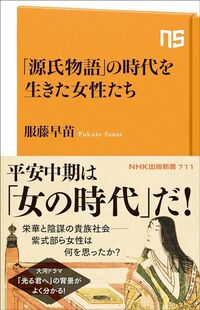教養ある女性だった定子を清少納言は徹底的に賛美した
この辞世の歌でもわかるように、定子は漢文、和歌などの素養のある女性でした。定子に仕えた清少納言が『枕草子』の有名なエピソードで書いたように、そもそも漢文の知識がなければ、白居易の詩に基づいて「香炉峰の雪はいかがであろう」という問いかけはできません。

清少納言は『枕草子』で、そんな定子の賢さや一条天皇との仲睦まじさ、夫婦と子どもたちのほほえましい団らんについて綴っていますが、定子を襲った悲劇についてはけっして書きませんでした。最後まで、定子賛美を繰り返しています。
それゆえに一般的には、皇后定子は美しく賢く、帝に深く愛された皇后、皇子まで産んだ非の打ちどころのない姫といったキラキラしたイメージになっていますが、父・道隆亡き後、彰子を国母にしたいと願う道長にとっては、じゃまな存在であったことは間違いありません。貴族たちから無視されるなど、辛い仕打ちを受けることも多かった人生でした。
ただ、そんな宮廷の権力争いの中でも、女性同士はお互いの身の上に同情を寄せ、助け合っていました。定子亡き後、彰子が皇子を産むまでは唯一の男子であった敦康親王を、彰子は養子としてきちんと育てますし、その第一子としての立場を守ろうともしています。また、敦康にとっては祖母に当たる詮子も、孫のことを気に掛けて贈り物などをしていました。絶大な権力を手にした道長に対しても、女性の立場はけっして弱くはなく、その後、彰子は詮子に続いて、国母、女院となり、宮廷で政治的な力を発揮していくことになります。
1947年生まれ。埼玉学園大学名誉教授。専門は平安時代史、女性史。東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。文学博士。著書に『家成立史の研究』(校倉書房)、『古代・中世の芸能と買売春』(明石書店)、『平安朝の母と子』『平安朝の女と男』(ともに中公新書)、『藤原彰子』(吉川弘文館)など。