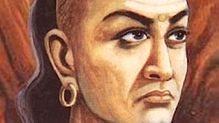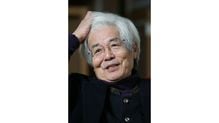ビジネスに活かされる古典の特徴
『実利論』に限らず、古今東西の古典を現代に活かそうとする際に大事な点がある。
それは、内容のすべてが適用可能ではないということである。ひとりの人物の手になるものであれ、複数の著者によるものであれ、執筆された時代の政治や社会、そして場所の状態や性格が一定程度反映されている。
21世紀の人間からすると、高度化・複雑化する状況にそぐわなかったり、時代錯誤的、あるいは差別的と感じられたりする点もなくはない。
それでも古典として今日に至るまで読み継がれ、時代や地域、本来のテーマを超えた広がりを見せているのは、物事の本質を鋭く突き、さまざまな場面や状況に応用できる汎用性を持ち、普遍性があることの証左である。
本来は兵法書である『孫子』がビジネスや生活全般に活かされているように、昨今の「戦略的思考」や「戦略本」において、はるか昔に記された古典に範をとるものが少なくないのは、このためにほかならない。
古代インドの国家統治論から何を学ぶか
これは『実利論』にも当てはまる。当然ながらマウリヤ朝の頃と現代とでは、内政であれ外交であれ、状況が大きく異なる。
王制だった古代インドに対して、現代インドは「世界最大の民主主義国」を標榜している(ただし、近年のインドは「民主主義の母」であるとも主張し、その原点を古代の政治体制に求めている)。
経済の多様化、人工知能や通信をはじめとするテクノロジーの驚異的な発達、政府を監視するメディアの存在、グローバリゼーションの進行と相互依存の深まりなど、他にも相違点を挙げればきりがない。
インド政府の指導層や政治家、官僚が『実利論』を参照しながら政策を決めているわけでもないはずだ。こうした背景を踏まえた上で、この古代インドの国家統治論からわたしたちは何を学ぶことができるだろうか。
第一に、『実利論』を通じてインドの伝統的な戦略思考の真髄を知ることができるという点である。