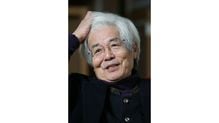良い物件を買えば誰でも3000万円儲けられる時代の必須スキル
そうした開発事業は、自治体が破格で用地を提供することも少なくなく、完成後の物件はお買い得になる場合が目立つ。
住民訴訟をした側から見ると、その自治体の住民の財産がお安く民間物件に変換されるわけだから、「けしからん物件」か「罪深い物件」となるわけだ。
「青空」(容積率)がプレゼントされるという、新しい払い下げの形に近いかもしれない。
産業革命が起こった英国では、繊維の原料の羊を育てるために、牧草地を囲い込むエンクロージャーが行われたが、現代日本ではタワマンなどをつくるために、行政とデベロッパーによる「公有地囲い込み運動」が盛んになりつつある。
どうすればそれがわかるかというと、早い段階から役所や企業を回り、住民運動の動きを見ておくことだ。「そんな記者みたいなことはできない」「市民運動は政治的で偏っている」と一般市民は腰が引けるだろうが、これは一度やったらやめられないほど面白い社会観察だ。
もう市民記者の時代は始まっている。記者でなくてもできるし、実益にもつながるかもしれない。一般人がそれを酒場で話すと「運動家」か「インテリ」(もしくは変人)に誤解されることもあるかもしれないが。
不動産がからむ訴訟やトラブルを、社会面的に訴訟や事件としてだけとらえてはいけない。「不動産の新しい方程式かもしれない」と考え、経済・経営・金融的にアプローチすることが必要だ。
「よい不動産を買っておけば誰でも3000万円もうけられる時代」の実現は、こうした開発最前線をリサーチする意欲のいかんにかかっている。

部屋は「かなり狭い」くらいがベスト
子育て中など、マイホームを買うタイミングは家族数が多いときが多い。
しかし、子どもは学校を卒業すれば独立するし、夫婦も別居や離婚という可能性がある。
幸い、マンションでは部屋があまりすぎるという事例はないが、中古住宅では家族数が減って2階部分を取り除く減築リフォームも実際に行われている。
高齢化すると、2階に上がる階段が大きなリスクとなる。高齢で階段を転げ落ちると骨折など大ケガにつながり、病院で動けなくなって認知症が進む場合も少なくない。体を動かさなくなると筋肉が落ち、歩けなくなるリスクもある。
したがって、分譲住宅は「ちょっと狭い」くらいがベターで、「かなり狭い」感じがベストといえるかもしれない。
家族の構成人数は右肩下がりが前提だから、そのトレンドに合わせるのだ。