心も治せる医者になれ
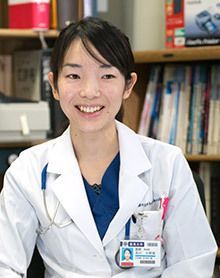
そのなかで私自身の医師としてのあり方を考える時、やっぱり大切にしてきたのは患者さんとの出会いだという気持ちがあります。
日本の国家試験は知識を問うことが重視されるけれど、日々の患者さんとのやり取りは教科書に載っていない大切なことを教えてくれます。そこから多くのことに気付いていくことで、初めて医師は成長していくのだと思うんです。
例えば、北海道時代に余市の小さな病院で研修をしていたときのことでした。入院している患者さんに、特殊な癌でとある大学病院に長く入院されていた方がいました。その方は最先端の治療を止め、余命を家族と過ごすため故郷の病院へ来たんですね。おそらく大学病院では多くの研修医や学生に会っているはずですし、点滴を失敗されたこともあったかと思うんです。それでも研修医の私に「点滴をとってみろ」と、朴訥(ぼくとつ)ながらもとても優しく接してくれた患者さんでした。
その病院でのローテーション期間が終わる際、挨拶に行った私に彼は「病気を治せる医者はいる。でも、君はそれだけではなく、心も治せる医者になれ」と言いました。あまり患者さんの前で泣いてはいけないのですが、涙が出るのを止められませんでした。その方は自分の人生をもって私に何かを教えてくれようとしていたからです。
10年近く医師を続けていると、失われていくものがあります。例えば、人の死に慣れてしまう。あまり悲しくなくなってくるし、心肺停止の患者さんが運ばれてきたとき、最初は本当にショックだったけれど、経験を積むと処置をして助かる人と助からない人がだんだんと分かってくるんです。それで助からないのであれば、家族といかにコミュニケーションをとるかを考えたり。プロフェッショナルな医療者の姿だと思いますが、ときどきそんなふうに死に慣れてしまいすぎることにも不安を覚えます。それが良いことなのか悪いことなのか、私にはまだ分からないから。
私の尊敬している外科医のある先生は、「その人が助かるかどうかよりも、その人のことをいかに思って、いかにその人のために医療をやったかが大事だ」と仰っていたものです。医師がどんなに頑張っても、患者さんが亡くなってしまうことはある。結果だけを見ていては前に進むことができなくなってしまいます。余市の患者さんが教えようとしてくれたのも、そうしたプロセスの大切さだったのでしょうね。それは教科書には載っていない、一人ひとりの医師が自分の体験として学んでいかなければならないことなのだと思います。















