独自の生成AI機能「Apple Intelligence」を搭載させたかった
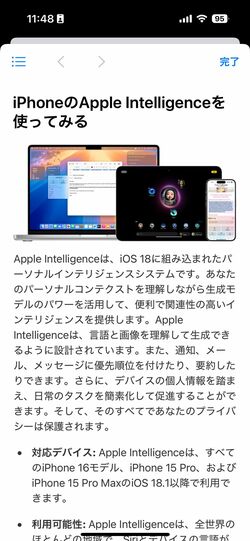
「Apple Intelligence」は、アップル独自の生成AIを用いて長いメールの内容を要約したり、自動で返信したり、写真をさまざまに加工したり、音声アシスタントSiriとより自然な言葉で会話できるようにしてくれるというもの。既存の生成AIサービスのほとんどはAI処理をオンラインの高性能サーバー上で行うのだが、「Apple Intelligence」はセキュリティやレスポンスなどの観点からこれをiPhone内で行う「オンデバイスAI」にこだわった。当然、そのためにはデバイス側に高度な処理性能が求められる。結果、「iPhone 16」および「iPhone 16e」は、最上位「iPhone 16 Pro」と同世代のプロセッサーと大容量メモリを搭載することになった。
生成AI活用において、GoogleやマイクロソフトらGAFAMのライバルたち、そして新興Open AIらに後れを取っていると言われるアップルは、ここで一気に巻き返したい気持ちがあったのだろう。そのためにはユーザーを一人でも増やす必要があるというわけだ。

ここから先は無料会員限定です。
無料会員登録で今すぐ全文が読めます。
- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信
- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能
- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能
- 記事をブックマーク可能















