未来の作家が参考にできる記録として
——『東京ディストピア日記』では、新型コロナウイルスのニュースが流れ始めた2020年1月26日から、2回目の緊急事態宣言が出た直後の2021年1月9日まで、激動の1年を綴っています。この日記をつけようと思ったのはなぜですか。
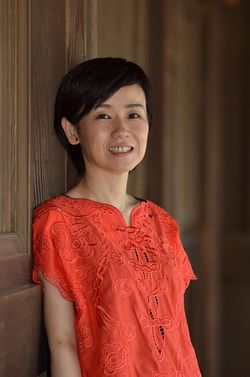
【桜庭一樹さん(以下、桜庭)】10年前の東日本大震災時のことを振り返ったとき、時系列をごっちゃにして記憶しているなと思ったんです。
最初の1カ月ぐらいに起こったことの順番を忘れているし、自分が後から考えたことを当時から考えていたかのように思っている。それで、新型コロナウイルスの感染拡大でバタバタしてきた2020年の2月ぐらいから記録を始めました。5年後、10年後、またはもっと先の人や未来の作家が今のことを知りたいと思ったとき、日記形式で残っているものが多ければ多いほど記録として役に立つんじゃないかと思いました。
——Instagramにアップしていた文章が基になっているそうですが、書籍化に当たって、残しておこうと思ったのはどんなところですか?
【桜庭】本には重要なところを選んで圧縮しましたが、特に意識の変化の過程は残したいと思いました。例えば、コロナ禍も今ではもう長くなりましたが、去年2月ぐらいの時点では、「このあとの2週間ぐらいはたいへんかも」と甘く見ていました。最初の緊急事態宣言が明けたときには、「これでひと山越えた」と思ったとか、そういうことって忘れてしまう。マスクが買えないとか、和牛券が配られるらしいとか、現在とは全然違う状況って記憶に残らないんですよね。
















