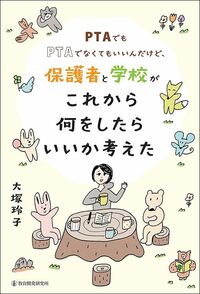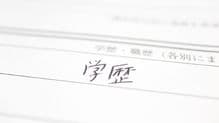「仕事をしなければいけない」と考えるから間違った道へ進む
不登校の保護者の会、みなさんはどう思われたでしょうか? 「こういうの、自校でもやってみたいな」と思った方も、きっといるでしょう。
ちなみに、Kさんが会を始めるきっかけとなった、習志野市のPTAの「不登校の保護者の会」の話は、拙著『PTAでもPTAでなくてもいいんだけど、保護者と学校がこれから何をしたらいいか考えた』でたっぷり紹介しています。興味がある方は是非、ご覧ください。
PTA活動というと「ただのおしゃべりなんてダメでしょ。なにか『仕事』をしなければいけないんじゃない?」と思われがちですが、本当にそうなのでしょうか。
「クジ引きであたったから」と仕方なく広報紙をつくったり、「ポイントを一番ラクに貯められるから」とベルマークを切り貼りしたりするより、保護者同士が自ら「集まりたい」と思って集まり、話をして考え合うほうが、ずっと意味があることのように筆者には思えます。
なぜPTAにはドス黒い空気が流れがちなのか
PTAを「仕事」にしてしまうから、「我慢してやるのが当たり前」「やらない人はズルい」といった、ドス黒い空気が生まれてしまうのでは?
もちろん、これまでPTAがしてきたような学校のお手伝いも、やりたい人がいたらやればいいのです(他の人を無理に巻き込まない前提で)。ただ同時に、もっと「保護者自身が求めるもの」も、大事にしていいんじゃないかと思うのです。それはきっと、子どもや学校にもいい影響をもたらすのでは――そんな確信があります。
1971 年生まれ。東京女子大学文理学部社会学科卒業。PTAなどの保護者組織や、多様な形の家族について取材、執筆。著書は『ルポ 定形外家族』(SB新書)、『PTAをけっこうラクにたのしくする本』『オトナ婚です、わたしたち』(太郎次郎社エディタス)ほか。共著は『子どもの人権をまもるために』(晶文社)、『ブラック校則』(東洋館出版社)など。東洋経済オンラインで「おとなたちには、わからない。」、「月刊 教職研修」で「学校と保護者のこれからを探す旅」を連載。ひとり親。定形外かぞく(家族のダイバーシティ)代表。