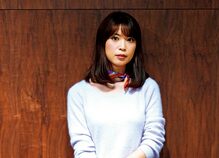「母の本棚」が新聞記者の私の基礎をつくった
私が記者という仕事に憧れるようになったのは、中学生の頃です。母親から「これ読んでみたら?」と手渡された『南ア・アパルトヘイト共和国』(大月書店)という本に衝撃を受けたんです。著者は吉田ルイ子さんというフォトジャーナリストで、南アフリカで行われていたアパルトヘイト(人種隔離政策)の実態を、写真と文章でつづったものでした。白人でない者はタクシーに乗れず、水を飲む場所も分けられている。学校で習って知っているつもりでしたが、実際に理不尽な世界を目の当たりにして、言葉を失いました。
▼自分を苦しめている「悩み」の正体は……
母はいつも世界の貧困や不平等について書かれた本やテレビ番組を私にすすめてくれていたのですが、その母の本棚で見つけた『「道(タオ)」の教え』も、忘れられない一冊。著者の島田明徳さんは、母が尊敬していた気功の先生で、この本には、自分を苦しめている悩みをどうすれば解決できるかが書かれていた。一言でいうと、「悩みの原因は、それを問題と感じている自分自身にある」ということなんです。

私たちが、ある出来事にどのように反応するかは、そのときの思考の状態によって決まる。その思考とは、あくまでも「私」の思いや考えによるもので、「私」を通してしか物事を判断できない以上、1つの出来事を客観的にとらえることはできない。だから、悩みから解放されるには、事実と「自分の思い」を切り分けて考えることが大事なんだと。
当時、私は高校生でしたが、ちょうど恋愛や勉強や部活のことで悩んでいたので、これを読んで気が楽になったというか、救われたんですよ。
部活は水泳部でしたが、私は「きついメニューをこなさないと、絶対にうまくならない」と後輩にもやらせて、「スパルタ」と言われていたんです(笑)。でも、この本を読んで「あんまり、とらわれすぎちゃいけないな」と後輩の意見を聞きながらメニューを変えるようになった。
恋愛も、失恋ばかりで「どうして?」と思い悩んでいたのが、「この人が好きっていうのは、自分でそう思い込んでるだけかな」と、一呼吸置けるようになりました。
社会人になってからも、エゴというか自分の思いを通して物事を見てしまうことは多いですけどね。たとえば、衆院選の予測記事で「与党が300超えか」なんて見出しを見た瞬間、「大問題だ!」となるんですけど(笑)、他の人から見れば、北朝鮮情勢が緊迫するなかで、安定与党は必要という見方もできるかもしれない。いったん冷静になって、客観視する習慣がついたのは、この本のおかげかもしれません。
じつは母にこの本をすすめたのは、母の中学時代からの親友の方でした。母も私と同じで、「一生懸命やらねば!」と思い込んでのめりこむ人だったので、母自身もこの本や先生から教えを受けて、いろんな意味で解き放たれたのかな、と今になって思います。
記者になってからは、清水潔さんの『遺言―桶川ストーカー殺人事件の深層』(新潮社)を読んで、こんな人がいるのかと圧倒されました。記者という仕事は、当局からいかに特ダネを取るかが勝負といわれていますけど、彼はその当局の先を行って、独自のルートで犯人を絞り込んで特定して、その情報をもとに警察が動くという……。まねのできないすごさを感じると同時に、記者が目指すべきニュースは、当局が意図的に、もしくは発表を前提で流すようなものではいけないと強く意識するようになりました。