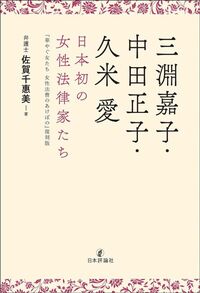お嬢様育ちの嘉子が福島の農家に疎開して田植えを手伝う
戦争が激しくなるにつれ、生活が苦しくなった。長男の芳武が生まれて約1年後の昭和19年2月。住んでいた麻布笄町の借家は、軍の命令で引き倒された。空襲による火事を防ぐためであろう。嘉子らは高樹町に移った。しかし、翌20年5月。この家も空襲で焼けた。弟の一郎の妻である嘉根と一緒に、嘉子は疎開した。嘉根は生まれたばかりの娘を連れていた。芳武は、2歳半だった。
4人は6カ月間、福島県の坂下の農家で暮らした。輝彦は疎開先の様子をこう語る。
豊かな家で育てられた彼女である。大変な苦労であったろう。
終戦前後の3年間で家族を次々と失い、4つの葬式を出す
終戦をはさんで3年の間に、嘉子は4つの葬式を出した。
まず、彼女のすぐ下の弟、一郎が戦死(昭和19年〔1944年〕6月)。彼は、2度目の応召で沖縄に向かっていた。船が鹿児島湾の沖で、沈没した。
武藤家の長男が亡くなったわけである。しかも、遺骨は帰らなかった。遺品だけが父のもとに返された。
次に、嘉子の夫が軍隊で病死した(昭和21年〔1946年〕5月)。和田芳夫は病気をするために兵隊に行ったようなものだった。中国に渡るとすぐ発病。上海で入院した。そして、長崎の陸軍病院までは帰って来ていた。
芳夫と嘉子夫婦の一人息子である和田芳武は、筆者にこう語った。
電報が家に着いたときのことは、今でも覚えています。家中、驚きましたから」
筆者「まだ3歳でいらしたでしょう。よく、記憶にありますね」
芳武「ええ。強い印象でした」
嘉子は当時、明治大学の女子部で、民法を教えていた。ちょうど女子部で勉強していた、佐賀小里は言う。筆者の義母である。
涙で顔が紫色になった人を見るのは、私は初めて。『夫が死ぬと、こんなにつらいめにあうのか。それなら、私は結婚はするまい』と思ったほどでした」