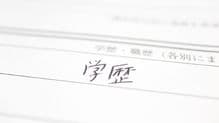PTAが学校側をかばうケースもある
学校外の窓口設置に加え、われわれ保護者もこういった教員の存在を知ったときに、声をあげることが必要だろう。わが子が直接被害を受けていなくても、ほかの子どもが理不尽な体罰や暴言を受けていれば、その状況を目にする子どもたちは無力感を抱き、傷つき、間接的に大きな被害を受け得る。
校長や教育委員会の責任を追及するだけでは、おそらく今後も変わらないだろう。「モンペ」と思われないよう学校にはたてつかないのが一番だ――問題があると知りながら、もしそんな考えで口を閉ざすことがあれば、保護者も罪深い。
欧州は多くの学校に、教職員の任用にある程度保護者の意見を取り入れる仕組みがあるが、日本では保護者が教職員の任免に口を出すことがタブー視されている。いまも多くのPTAの規約には「学校の人事に干渉しない」という文面があり、指導死などの事案が発生すると、PTAが学校側について教員をかばうケースも見られる。保護者や子どもの視点で学校側に対等にモノが言えない保護者組織に、どんな存在意義があるというのだろう。
「保護者が保護するのは『子どもたちの権利』であり、自分の子どもを守る一番の責任は、保護者にある」。これは筆者が以前取材した教育学者・リヒテルズ直子さんの言葉だ。保護者には学校からどう思われようと、子どもを守らねばならないときがある、ということではな
ただでさえ昨今負担の大きい教員にとって、このような提言は驚異と感じられるかもしれない。もちろん保護者が勝手な思い込みで善良な教職員を追い込むような事態は避けねばならないが、多数の子どもが問題を訴えているような場合、「保護者」が黙って見過ごすわけにはいかない。
1971 年生まれ。東京女子大学文理学部社会学科卒業。PTAなどの保護者組織や、多様な形の家族について取材、執筆。著書は『ルポ 定形外家族』(SB新書)、『PTAをけっこうラクにたのしくする本』『オトナ婚です、わたしたち』(太郎次郎社エディタス)ほか。共著は『子どもの人権をまもるために』(晶文社)、『ブラック校則』(東洋館出版社)など。東洋経済オンラインで「おとなたちには、わからない。」、「月刊 教職研修」で「学校と保護者のこれからを探す旅」を連載。ひとり親。定形外かぞく(家族のダイバーシティ)代表。