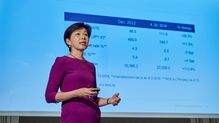「美しく可哀想な弱者」でなければ受け入れられないのか
本作の内田英治監督はTwitterで次のように述べている。
「多様な意見がある。素晴らしいこと。人の数だけ意見が富んでる。素晴らしいこと。でも自分の映画を社会的にはしない。これは娯楽。娯楽映画で問題の第一歩を感じれればいい。社会問題は誰も見ない。映画祭やSNSでインテリ気取りが唸り議論するだけ。なので娯楽です。多くの人に観てほしい。それだけ」
劇中で中小企業のオジサン面接官が、採用面接を受けにきた凪沙をひと目見て「いま、はやってますよね、LGBT」と無邪気に言い放つ。本人は「特別な、可哀想な人たちに理解を示した」つもり。だが横に座る女性社員に、発言をコテンパンに非難されるのだ。そんな、ものすごくリアルな社会観察力に優れたセリフのやり取りを書ける監督が、「娯楽に社会性を求めるな」と発言する意味とは、一体何だろう。
映画は娯楽との意見に、私も大いに賛同し、大歓迎する。しかし、性的マイノリティがエモい死に方をすることなく、「多数派同様に」生き続ける映画は、娯楽としては成立しないのだろうか。性的マイノリティは、特別な死を迎えなければ物語にはならないのだろうか。幸せな性的マイノリティは、誰かが考える「こうあるべきマイノリティ像」とは違うのだろうか。私たちの世界は、あとどれだけ「美しく可哀想な弱者」を見なければ、マイノリティの存在を普通に受け入れられないのだろうか。
「きれいごと」は、果たしてどっちだろう。このモヤモヤ感もまた、『ミッドナイトスワン』という映画が私たちに残した“問い”のひとつなのかもしれない。
1973年、京都府生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業。時事、カルチャー、政治経済、子育て・教育など多くの分野で執筆中。著書に『オタク中年女子のすすめ』『女子の生き様は顔に出る』ほか。