
「東京リベンジャーズ」のような抗争が続いていた戦国の関東
天文10年(1541)7月、北条氏綱が病死した。その息子、北条氏康の名を轟かせることになる「河越城合戦」は、この4、5年後のことである。本来なら関東のトップは、下総古河におわせられる関東公方(※1)・足利晴氏のはずであった。だが、関東の事実上の天下人は氏綱と化していた。どうしてそうなってしまっていたのか。
ある時、公方の一族で内輪もめがあった。永正15年(1518)、下総の足利義明が独立して、「小弓公方」として振る舞うようになったのだ。もちろん支持する層あってのことだ。このため、関東公方は、小弓公方の義明と、古河公方の晴氏に分裂することになった。これが関東公方凋落の一因となっていく。
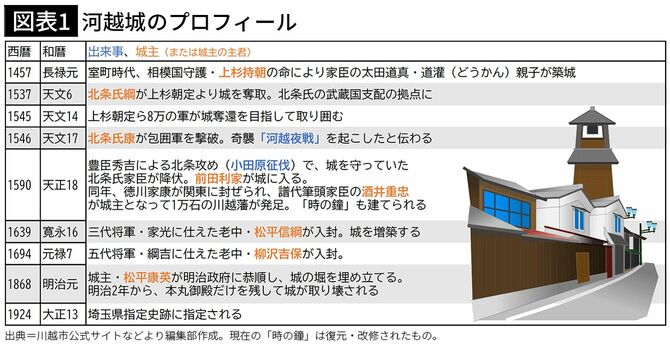
関東公方の足利晴氏は足利義明にケンカを売られ、氏綱を頼る
古河の晴氏は、先代公方・足利高基の息子である。小弓の義明は、高基の弟である。どちらも血筋としては優劣つけがたい。だが、キングはふたりもいらない。晴氏と義明の確執は深く、ガンマンがピストルに手をかけながら互いに互いを睨み合う状態が長く続いた。そんな天文6年(1537)5月、風が吹く。
ダンブルウィード(※2)のように転がったのは、安房の里見義堯だった。これからは古河ではなく、小弓の時代だと立場を明確にしたのだ。それまで情勢を見張っていた関東の領主層が一気に旗幟を鮮明にしていく。古河派、小弓派が互いに争い合う。もはや決戦しかない。
このとき、晴氏の片腕となるべきは、関東管領である山内上杉家当主・憲政であった。だが、憲政はまだ19歳である。しかもこの時期、史料上では晴氏が憲政を関東管領として認めていた様子がない。実績不足の憲政は、求心力が育っていなかった。
晴氏がひとまずすぐに頼れるのは、憲政よりも、氏綱だった。伊豆相模を拠点とする新興勢力・北条家の当主である。
(※1)室町幕府が関東10カ国を統治するために設置した「鎌倉公方」を足利尊氏の四男・足利基氏の子孫が世襲。「関東公方(管領)」はその鎌倉公方の補佐役。
(※2)西部劇の決闘シーンでよく見られる球状になった枯れ草。
















