加害されたあと「男性性」を取り戻そうとする被害者
これまでの研究からは、性暴力に遭った男性のその後の反応として、暴力的な、つまり「男性的な」振る舞いをする傾向があることが指摘されています。もちろん、傾向であってすべての被害者がそうなるわけではありませんし、また、暴力的な振る舞いを「男性的」と見る視点についても、自己省察が必要です。
しかし、一方では男性性を取り戻そうとするプロセスに入る人もいて、その場合には被害を否定し蓋をする傾向が見られます。また他方では、被害者であると受け止めたことで、自身の男性という性別について葛藤を抱えることがあります。
素朴な男らしさを多かれ少なかれ期待され、また気づかぬうちにその男性というポジションで得られる利益を享受して生きていた男性被害者が、自らの男性というカテゴリーと向き合わざるを得ないことが、性暴力被害体験の一側面としてあります。
男性性の混乱という状態に表れているように、自分のセクシュアリティを相対化し考える必要が生まれてくるため、その結果として自身の持つ男性特権、男性というカテゴリーの権力性と被害体験に整合性が取れなくなってくるのです。
男性特権も手にしながら性被害を理解することは困難
男性が性暴力被害に遭うことが理解されづらい状況というのは、この性に基づく社会のルールが影響しているのですが、裏面ではそのルールの中である種の恩恵に与っている状態でもあります。女性が劣位に置かれているために「女性化」という問題が生じ、同性愛が差別されるために、性暴力被害が同性愛の問題として排除されている。これらが問題となるのはそもそもそういった差別が存在するためです。
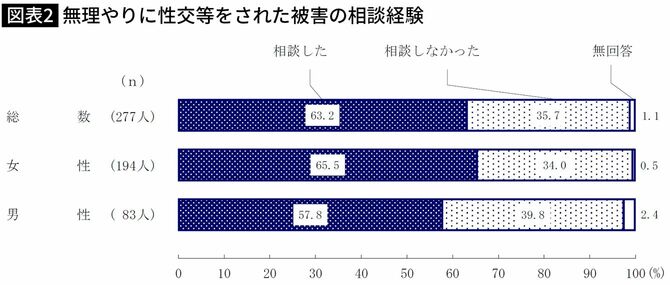
同様に、男性特権が得られる社会というのは、男性の理想的なイメージが称揚され、一方で女性差別やマイノリティ差別を作り出している状況のことです。ですから、男性が現状の男性らしさを維持し、男性特権も手にしながら、男性の性暴力被害を理解することは困難でしょう。
男性の性暴力被害における困難の一つは、男性優位の社会のルールに沿って生きるならば、男らしく生きることで性暴力被害を否定するか、はたまたルールに背いて被害経験を受け止めるかを迫られてしまう点です。
















