※本稿は、宮﨑浩一、西岡真由美『男性の性暴力被害』(集英社新書)の一部を再編集したものです。

男性への性暴力はなぜ世間から見えなくなってしまうのか
男性の性暴力被害が不可視であるとはどのような意味でしょうか。不可視ということは見えていないということです。しかし、現実には男の子も成人の男性も性暴力被害に遭っています。この事実と矛盾する「見えない問題」とはどのようなことなのでしょうか。
男性のレイプ神話というものがあります。
レイプという性暴力について何らかの理由をつけて暴力ではないと正当化するための誤った信念のことです。そして、レイプ神話は、被害者を責める言説となり、二次被害を生むセカンドレイプとなります。
レイプ神話は四つのタイプに分けられています。
「酔っていたなら多少は責任があるだろう」「暴力や脅迫がないなら、レイプじゃないだろう」
2)申し立てに疑いを投げかける信念
「復讐や嘘で相手をはめようとしているんだろう」「被害から時間が経っているから、信じがたい」
3)加害者を免罪する信念
「男は性欲を我慢できないから仕方ない」「女性のほうが誘うようなことをしていたのではないのか」
4)「本当のレイプ」がどのようなものかについての信念
「レイプは知らない人から暗がりでされるもの」「常に暴力的なもの」「男性はレイプされない」「女性は加害者にならない」
レイプ神話による誤解から、被害者が責められてしまう
被害者の言動を責め、その告発を信じず、加害者を擁護することはよくあります。例に挙げられているような言葉が文字通りにあるいは、あからさまに使われている状況はそれほど目にしていないかもしれませんが、被害者擁護のようなこと、または、「差別ではないけれど」などと断りを入れながら、レイプ神話をなぞるような言葉は投げつけられています。
さまざまなレイプ神話がありますが、男性被害者に対する神話としては次のようなものが挙げられます。
・「本当の」男は、レイプから身を守れる
・ゲイ男性だけが被害者および/または加害者
・男性はレイプによって影響されない(女性ほどではない)
・女性は男性に性的暴行を行えない
・男性へのレイプは刑務所内でのみ起こる
・同性からの性的暴行で同性愛になる
・同性愛と両性愛の人は不道徳で逸脱しているので、性的暴行に遭うに値する
・もし被害者が肉体的に反応したのなら、その行為を望んでいる
「男は強く、女は弱い」という幻想から信じてもらえない
ここには被害者非難、その告発への疑い、加害者擁護が見て取れます。また、「本当のレイプ」は、男性加害者が女性に対して行うもので、そうでなければ同性愛の問題ということになっています。
こうした信念は、強力なジェンダー規範を表しています。それは、男は強い、女は弱いといった二項対立のジェンダー関係が基準となった世界観です。そのため、男性が性暴力の被害に遭うということは、そもそも信じられないことか、もしくは「女々しく、弱い」劣った男とされたり、そうでなければ性的指向に原因を求められたりしてしまいます。このことによって、強い男という幻想は維持されながら、男性被害者は不可視となっていくのです。
男性の性暴力被害の不可視とは、ジェンダーとセクシュアリティの規範によってさまざまな性のあり方が無視され、男性=加害者、女性=被害者という男女二元論の非常に狭いルールから外れたことによって被害事実それ自体が人々から認められないことです。この中には、被害当事者も含まれているため、それによって声を上げづらく、被害は隠されていきます。
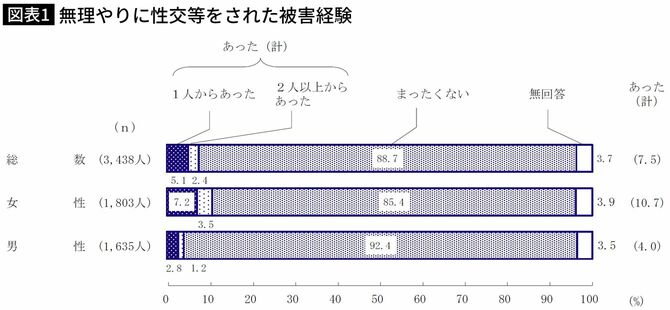
男性優位な社会ではかえって被害男性が偏見の目で見られる
ジェンダーが男女の権力関係を表すように、ジェンダーやセクシュアリティの規範が存在しているのは、この社会が特定の性的なあり方を認めそれ以外を排除している状況があるからです。これはつまり、誕生したときに社会に登録された性別の通りに生きられるシスジェンダーで、異性を愛する男性が有利に生きられる仕組みです。
男性の性暴力被害者が社会の偏見によって影響を受けている不可視性の裏面には、男性優位な社会において男性であるというだけで受け取れる有利な利益もまたあります。この両面性こそが、男性というカテゴリーが持っている被害の理解の難しさでもあります。
男性被害者が自身の不快な体験を、性的虐待、レイプ、セクハラなどの、性暴力と関連する言葉を使って名づけることは、その後の回復プロセスにおいて重要な起点となります。性暴力の被害者であること、そして男性であることを両立させるのはその後のあり方を左右する場合があります。
加害されたあと「男性性」を取り戻そうとする被害者
これまでの研究からは、性暴力に遭った男性のその後の反応として、暴力的な、つまり「男性的な」振る舞いをする傾向があることが指摘されています。もちろん、傾向であってすべての被害者がそうなるわけではありませんし、また、暴力的な振る舞いを「男性的」と見る視点についても、自己省察が必要です。
しかし、一方では男性性を取り戻そうとするプロセスに入る人もいて、その場合には被害を否定し蓋をする傾向が見られます。また他方では、被害者であると受け止めたことで、自身の男性という性別について葛藤を抱えることがあります。
素朴な男らしさを多かれ少なかれ期待され、また気づかぬうちにその男性というポジションで得られる利益を享受して生きていた男性被害者が、自らの男性というカテゴリーと向き合わざるを得ないことが、性暴力被害体験の一側面としてあります。
男性性の混乱という状態に表れているように、自分のセクシュアリティを相対化し考える必要が生まれてくるため、その結果として自身の持つ男性特権、男性というカテゴリーの権力性と被害体験に整合性が取れなくなってくるのです。
男性特権も手にしながら性被害を理解することは困難
男性が性暴力被害に遭うことが理解されづらい状況というのは、この性に基づく社会のルールが影響しているのですが、裏面ではそのルールの中である種の恩恵に与っている状態でもあります。女性が劣位に置かれているために「女性化」という問題が生じ、同性愛が差別されるために、性暴力被害が同性愛の問題として排除されている。これらが問題となるのはそもそもそういった差別が存在するためです。
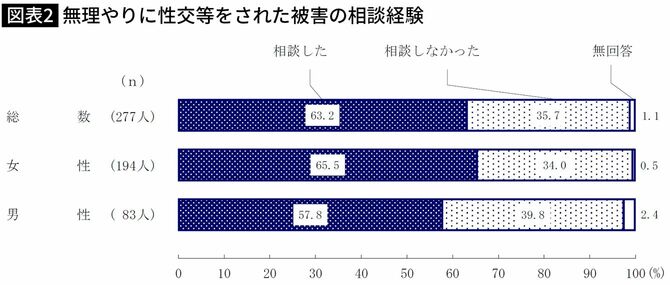
同様に、男性特権が得られる社会というのは、男性の理想的なイメージが称揚され、一方で女性差別やマイノリティ差別を作り出している状況のことです。ですから、男性が現状の男性らしさを維持し、男性特権も手にしながら、男性の性暴力被害を理解することは困難でしょう。
男性の性暴力被害における困難の一つは、男性優位の社会のルールに沿って生きるならば、男らしく生きることで性暴力被害を否定するか、はたまたルールに背いて被害経験を受け止めるかを迫られてしまう点です。
「性的いじめ」は性加害ではなく単なる「いじめ」と思われがち
暴行や脅迫が用いられる際も、性を用いた暴力という点は隠されることがあります。例えば、「性的いじめ」について考えてみましょう。加害者たちは特定の人を無視したり、暴言を投げつけたり、暴力を振るったりなどさまざまな行為の中で、性を用いた暴力を使います。
「いじめ」という一連の言動の中に性が紛れ込むと、そこに加害者の性的な動機を見つけにくく、身体の弱い部位を狙ったということで、性的な行為が性暴力としてではなく、いじめの一環として位置付けられることになります。
紛争下における男性や男児への性暴力についても研究で徐々に明らかになっていますが、性を用いた暴力は、統計上は非常に少ないものだと見なされていました。それはその加害が身体への暴行や拷問として計上され、性暴力として反映されていなかったからだと言われています。ある紛争下の報告書では男性や男児に2%の性暴力被害があったとされましたが、それらの証言で性器に対する暴力など複数の形態を含めてカウント調査したところ、29%まで上がったということです。
「半沢直樹」で描かれた男性への性的なパワハラシーン
2020年に放送されたドラマ「半沢直樹」(続編)では、失敗した部下を叱り、その際に性器をつかんで痛みを与えるというシーンがありました。その描写では性暴力という視点よりも、それに反応して足を閉じてしまう男性がコミカルに描かれ、その場にいた全員が注目し、白けた視線を送っていました。
性器をつかむことや、そこを蹴ることは、ふざけていること、単に弱い部分を狙っただけということにして、性的ではないような印象を与えることができます。パワハラやいじめといった「性的」要素が含まれないようなラベルを貼り、性暴力を隠すことができるのです。
同性間の性暴力に関しては、ホモフォビアに晒されその被害を開示しづらいことがあります。加害者も同様にそのレッテルを貼られる可能性がありながらも、それはあまり重視されません。なぜなら、ある行為が性暴力だと定義し伝える必要があるのが、常に被害者の側だからです。加害者のほうからは同性間の性行為ということを明らかにする必要がありません。さらに、「女性化」という性差別をもとにした力関係では、加害したほうが男らしく表象されるために、より隠れやすくなると言えるでしょう。

