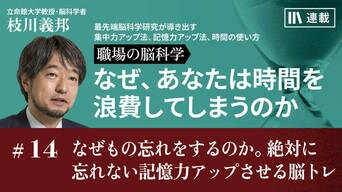なぜ新聞記者というキャリアを選んだのか?
なぜ、記者職を選んだのか。髙橋さんは言う。
「博士課程まで進んだのですが、僕は能力的に優秀でないうえ、学問を究めるストイックさに欠けていました。また、現在の妻と結婚話が出ていたことで、そろそろ経済的にも安定しないといけない……と思ったのが主な理由です」
それで就活らしきことを始めたが、年齢はすでに20代後半。一般企業への入社が難しい状況だったが、新聞社は30歳まで新卒採用の入社試験を受けることができた。親しい友人にも新聞社や放送局などマスメディアに進んだ者がいたので、就活のハードルも感じなかったという。
「結局、入社試験を受けられたのは毎日新聞だけでしたが、ダメ元で受けたら、合格。1社のみの就活で内定をもらい、運命を感じました。大学院は単位取得退学という形にして、28歳で新聞記者になったのです」
会社はもはや自分を必要としていないのか
記者としてのスタートは、福井支局の原発問題を担当。その後、広島支局で原爆・平和問題に取り組み、大阪本社社会部で大阪府警捜査1〜4の全ナンバー課を担当した。一時期は遊軍記者として自由な取材活動も任され、エリート街道を進んでいたと言ってもいい。
「もともと僕は興味がある対象、人間にとことんのめり込むタイプ。寝食を忘れて取材し、記事を書き続けました。幸いにも社内の賞もたくさんいただいて、充実した記者生活を送っていました。本当に楽しかったので、定年まで記者を続けるつもりでいたのです」
ところが、54歳の時、毎日新聞社は経営難からリストラを断行し、高橋さんは早期退職の勧告を受けてしまう。頭打ちだった給与水準がさらに大きく下がることが伝えられ、会社に残ったとしても専業主婦の妻と3人の子供を抱える身では経済的に苦しくなることは明らか。
さらに人一倍仕事に誇りを持っていた髙橋さんは屈辱的な思いをする。
「これまで社内で受賞した記事についても、経費と労力がかかっただけだ、と幹部から批判的に見られていたことも分かり、もう自分は必要ないのだ、潮時かもしれないと感じました」