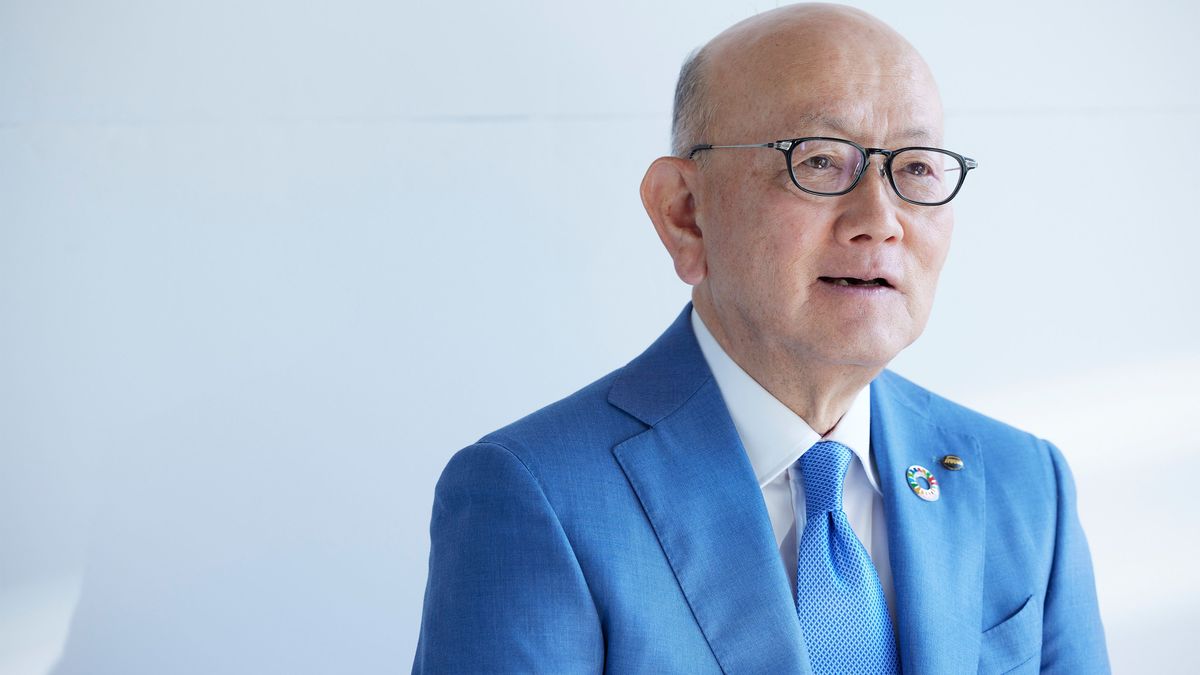「考えることの楽しさ」を知ってもらいたい
――スライスされた仕事をしている人たちは、気づくチャンス自体がなかなかないと思うんです。たとえばこの『マーケティング思考の可能性』を三日で読め、と言われても、日々の仕事が忙しくて余裕がない。でも、ゆっくりでもいいから読んでいくことで、「あとがき」の水道管の話に辿り着き、「俺は水道管で終わるのは嫌だ。この本に書かれているように、相手の中に棲み込んで考えることで、俺はオリジナリティのある次の段階に行けるんじゃないか」と気づくことができるのではないかと。
石井 そうなってもらえると嬉しいですね。「考えることの楽しさ」を知ってもらいたいという思いは、大学の学長という仕事をしている身には、大きなテーマなんです。今は若い人たちの間に「学ぶこと、勉強することは辛いことだ」という考え方が浸透しすぎている。学ぶことは楽しいんです。だけど、それを小学校、中学校、高校、そして大学でも、しんどい作業として教え込んできた。今や、勉強という言葉は、しんどい作業の代名詞になっています(笑)。
教育には「入り」と「出」があります。「入り」は、方程式や歴史や地理、英語の単語を覚えること。いつか役に立つと言って、学校は子どもたちにそれを覚えさせてきた。まあ、それほど役に立つかどうかわからないのだけれど(笑)。要するに、今までの教育は「入り」ばかり計って、「出」はお前自身が決めろというやり方だったんです。
昔の私が通った時代の大学であれば、コピーの機械もウエブもなかったから、図書館や研究室の先生の頭の中にしか知識と知恵はなかった。だから先生の傍に行き、図書館に潜り込んで筆写しながら勉強したわけです。それを「学ぶ」と言っていたわけです。「入り」ばかりだった。だから知識を持っている人は偉く、そこで知識をもらうことは大事なことだったわけです。
ところが今はもう時代が違う。知識は大学以外のいろんなところで入れることができる。そういう意味では「入り」の値打ちは相対的に減ってきている。では今、大学の意義はどこにあるのか。私は、「出」の場をつくっていくことに意義があると思っているんです。自分の持っている知識、知見、理論、経験、友だちのネットワークを総合的に使える場を用意してあげるという役が。
それが前回言った「実学」なんです。例えば、ドンクが「夕食にパンを提供するにはどうしたらいいでしょうか」というテーマを持ち込んできて、学生たちがドンクや消費者の立場になって考え、そこに自分の理論や経験を加えて、考える。そういう「出」の局面をつくってあげることが、今の大学の意義ではないかと思っているんです。
ベーカリーの「ドンク」が 簡単・豪華ディナーの新提案!
[ 記事を読む ]
石井 「ドンクさん、こういうことで困ってるんやな」と気づき、その問題にコミットしていくことで、次々に「あれも勉強しておかなあかん」「あの人に聞きにいかなあかんな」と、いっぱい知識欲、好奇心が出てくる。それが学ぶ楽しさに結び付くんです。そういう楽しさというものは、今までの大学では、あまり教える機会がなかったんじゃないかなと。
――かつては「学ぶことは楽しさがあるんだよ」ということは、わざわざ言わなくてもわかっていた、ということでしょうか。
石井 いや、わかっていなかったと思いますよ(笑)。先生も学生も「入り」ばかりで、方程式を覚えてそれを再現するだけで「ああ、賢いなあ」と言われて喜んでいたんじゃないですか。まあ、その能力は官僚になったりするときには悪い能力ではないので、それはそれで良かったのでしょうけどね。
――東京都内の大きな書店のビジネス書売り場で働いている人に聞いた話ですが、「以前は、うちのお客さんは本を複数冊買っていた。今は平積みのベストセラー一冊しか買わない」と。以前は、お客さんは上の人文書のフロアにも行っていたというんです。今はおカネがないからなのか、スライスされて忙しいからなのか、「触角」がビジネス書売り場以外に伸びていない。
石井 学生であれ、企業の現場にいる人であれ、今の若い人は、繭の中に何重にも取り囲まれていて、自分はもう繭の外には出られないと思っているのかもしれませんね。その繭を破って外に出ていくという発想そのものを持つことがないのかもしれない。