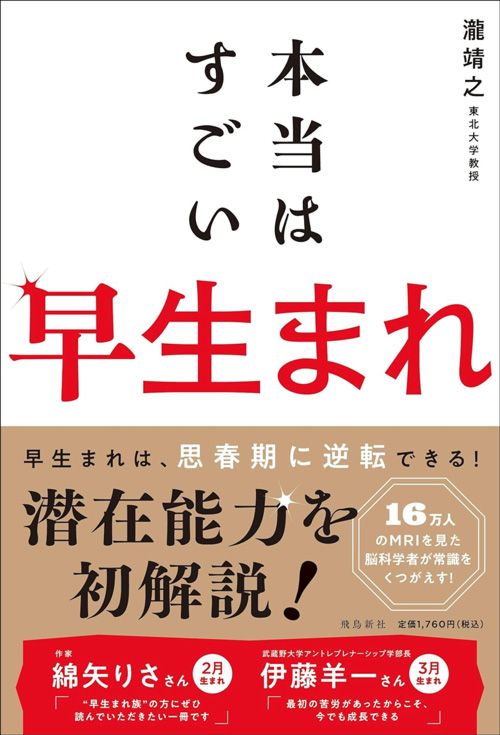能力を伸ばすカギは「自己肯定感」
早生まれの子どもは、「先生や友だちから認められていない」と感じていることも、この調査が明らかにしたことです。対人関係の苦手意識も、このような「周囲はわかってくれない」という気持ちに起因しているのかもしれません。
実は、これはとても大きな問題です。
自分のことを大切だと思える「自己肯定感」や、自分が頑張ることで何かを達成できると思える「自己効力感」は、人の能力を大きく左右する要素であることが数々の研究で明らかにされています。
「自己肯定感が高いほど大学の成績が高い(※3)」、「高校生の自己効力感と学力の関係から、自己効力感は学力向上の大きな要因であることが明らかになった(※4)」など、「自己肯定感・自己効力感が高いほど、学力も高い」ということを、これらの研究は示しています。つまり、「人間の能力は、自己肯定感・自己効力感によって左右される」ということです。
※3 Seyyed N. Hosseini, et al. Locus of Control or Self-Esteem; Which One is the Best Predictor of Academic Achievement in Iranian College Students. Iran J Psychiatry Behavioral Sciences, 2016 Mar 15;10(1):e2602.
※4 Shahrzad Elahi Motlagh, et. al. The relationship between self-efficacy and academic achievement in high school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 765-768, 2011.
早生まれの人の成績が振るわないとしたら、それは自己肯定感・自己効力感が低いからかもしれません。これらの感情の高低は、生まれつきのものではなく、高くもなり、低くもなります。「いかに高い状態にして維持するか」が、分かれ目になるのです。
早生まれの子には伸びしろがある
「早生まれの人はなぜ不利なのか」という視点で論文を読むと、逆説的に、早生まれの伸びしろがみえてきます。
今回の論文から読み取れるのは、「非認知能力を高める子育てをすれば、早生まれの子は伸びる可能性もあるのでは」と考えられることです。
この論文からだけでなく、私自身は、他にも「早生まれは有利」といえる理由があると考えています。脳科学の立場で考えれば、脳が若いうちに多くの刺激を受けることは、プラスのことだからです。
なぜ有利なのかについては、本書を通じてじっくりと説明をしていきたいと思います。