――企業によるサステナビリティの捉え方について、どう感じていますか。
【八林】ガバナンスも含めてこれから自社がどうあるべきかを追求していくと、やはり「サステナビリティを当たり前にやっていく」という状態にたどり着くのだと思います。事業活動を長く続けていれば、どうしても短期的な目線になってしまったり、いろいろなリスクから目をそらしてしまったり、逆にチャンスがあるのに気付かないといったことが起こり得るでしょう。それらを複数の指標を用いて定量評価し、明らかにしていくのが現在の潮流だと思います。昨今、気候変動に伴う自然災害の頻発や地政学的リスクが高まり、より不安定で不確実な要素が増えています。そこでデータなどを用いて客観的に現状や今後を予測し、「いかに企業価値を落とさないように活動できるか」が、特に投資の観点では重要な目安となっていると言えます。
後ろ向きな思考から脱却し次の動きへとつなげる
――組織的に取り組んでいく上で、どのようなことがポイントですか。

株式会社エスプールブルードットグリーン
取締役社長
2006年、環境省入省。カーボン・クレジットの制度設計などに携わる。10年に北海道下川町役場に転職し、環境未来都市など地域政策形成、モデル事業を手掛ける。18年に一般社団法人集落自立化支援センター設立、代表理事就任。20年より現職。
【八林】サステナビリティにはわれわれが専門とする気候変動の領域をはじめ、生物多様性、人権などいくつものテーマがあります。まずは経営トップがしっかりと自社の課題と向き合い、方針に落とし込むことが必要だと思います。どこにフォーカスするかはさまざまですが、あらゆる企業に共通して深く関係するのは「カーボンニュートラル」という大目標です。GHGは何十年もかけて算出方法が確立され、リスクと機会分析の手法も進化しています。それを「軸」として事業戦略を組み立てることが重要です。
――現状では後手に回っている部分もあるでしょうか。
【八林】欧州主導による開示基準などに対応しなければならない状況があり、コストがかかることもあって後ろ向きの発想になってしまう企業は少なくありません。そうではなく、CDPのスコアやTCFDの開示を「内発的な変革を促すために使う」とする思考への転換が大切だと思います。
近年ではZEB(ゼブ/ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)などのように、国や業界による日本の技術をうまく生かせる基準づくりが進められています。サステナビリティ情報開示においても、国、企業、団体などが連携して日本の強みを生かせる基準を設け、ビジネスチャンスにつなげていく、そんな動きがますます求められると考えます。
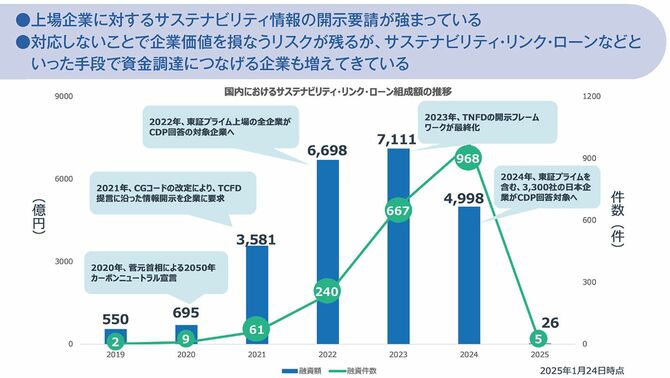
「丸投げ」にも対応できるサステナビリティ・エージェント
――自社で対応するにはハードルが高いでしょうか。
【八林】ガイドラインの読み込みには労力を要します。翻訳版もあるとはいえ原典は英語で、手探りで開示文書を作成するのはかなりの期間がかかるでしょう。積極的にサステナビリティ経営を推し進めているものの、CDPで思うようなスコアではなかったというケースも少なくありません。同じ設問を読んでも、企業それぞれのバイアスがかかって本来の意図とは異なる受け止め方をしてしまうことは珍しくないのです。
2011年からサステナビリティ経営支援を展開している当社には、これまでに支援してきた数多くの企業の知見が蓄積されています。業界によって持つべき長期・短期的な視野など、各社に応じたサポートを提供しています。例えばCDPのハイスコアを目指すための失点分析では、他社事例を踏まえて改善のための次のステップをご提案します。その際はTCFDやScope3算定など、関連して改善していくべき領域を含めた視点から対策を計画します。「何をしていいか分からない」という段階からでも全てをお任せいただける「サステナビリティ・エージェント」であることが当社の強みです。

――情報発信にも注力されています。
【八林】ウェビナー開催、メルマガ配信のほか、250社以上が所属する会員制コミュニティーサイト「Boyadge」を基盤としたオンライン上の交流や、実際に集まってのイベントなども実施しています。単なるコンサルティングサービスにとどまらず、当社が期待されている役割以上の「おせっかい」をすることで、企業間でもサステナビリティの担当者同士で学び合ったり、悩みを共有したりといった場として活発な交流が続いています。そうしたつながりを強めていくことで国内の取り組みを底上げし、共にカーボンニュートラルへと進んでいきたいと思っています。そうしたものを土台として、日本らしいサステナビリティ経営を基準化して海外にも発信していく、そんな未来をイメージしています。
サステナビリティ支援のプロ集団
エスプールブルードットグリーンはこれまでにプライム上場企業を中心に累計550社以上の企業へサステナビリティ経営支援を展開。CDPなどのESGレーティングにおけるスコア向上やTCFD・TNFD、GHG排出量など市場から求められる情報開示対応を支援。2024年におけるCDP回答支援では約200社への支援を実施。
伴走支援が導いた、さらなる「進化」

執行役員
テクノロジー統括 環境安全推進部長
加藤芳則氏
当社は、2020年まで自社のみでCDP質問書の回答をしていましたが、設問意図を正確に把握することに難しさを感じておりました。エスプールブルードットグリーンに支援をいただく中で、設問の正確な意図を理解することができ、設問に対して適切な回答を開示することができました。その結果として「A-」スコアの獲得ができておりその後も高いスコアを維持できております。支援のおかげでこれまでの取り組みの方向性が間違っていなかったことが確認できたことは大きな収穫でした。加えて、さらに取り組むべきことも明確にすることができており、指名報酬委員会の実施や社内炭素価格の設定など、サステナビリティ経営における新しい取り組みを進めています。
「良い意味でのお節介」CDP高スコア獲得

執行役員 グローバル戦略本部
サステナビリティ戦略室・ コーポレートコミュニケーション室長
北河広視氏
CDPの回答はお客さまからの要求にも関わるため、外部サポートを得て対応をしていましたが、物足りなさを感じていました。エスプールブルードットグリーンから提案を受け、丁寧な解説や詳細な模擬採点などに魅力を感じ、サポートをお願いすることにしました。支援が始まると、当社から要求しなくとも質問の背景や当社の活動状況を踏まえたご提案をいただき、良い意味で「お節介なサポート」をしていただいています。
当社はサステナビリティの取り組みを着実に進めてきたものの、開示基準に即してどう対応すべきか苦労していました。サポートのおかげで理解が深まり、現場の理解促進、われわれからの提案の質向上、そして当社の取り組みを適切に開示することにつながりました。結果、昨年のCDP気候変動Aスコアに加え水セキュリティでもA-を獲得できました。今後も社会課題の解決と経済合理性を両立した新規事業を生み出し、企業価値向上を目指していきます。
