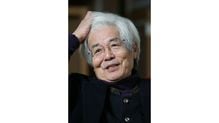出生率低下はお金のせい“だけ”ではない
もはや誰も驚かないことではあるが、日本の少子化スピードが危機的な状況だ。6月5日、厚生労働省が発表した2023年の人口動態統計で、1人の女性が一生に産む子どもの数の平均値を示す合計特殊出生率が1.20であったと明らかになった。
今年2月の厚労省発表でも知らされていた通り、そもそも出生数が戦後最少だった。子どもを出産する母の側においても、第1子出生時の平均年齢が初の31.0歳へと上昇し、ひと昔まえの感覚では「高齢出産」と呼ばれていたような初産年齢が、現代の日本では平均値となっている。
6月5日に成立した、子ども・子育て支援法などの改正法の内容は、かなり“金額的に”スピード感のある内容になっているが、その「異次元の」と銘打たれた少子化対策がどこまで実効的に日本の若い世代を出産・子育てへ導くのか。それは現実の出生数をどこまで増加させるのか、金銭的に支援されれば“子産み”は促進されるものなのか。そして出生率低下トレンドは反転しうるのか。
日本縮小のスピードの鈍化には貢献するであろうと一定の評価はしつつも、出生率の劇的な改善には疑念を隠せない識者が多いが、それは出生率低下の原因が経済的負担の問題だけではないからだ。
今回の“バトル”は何かが違う
「“子持ち様”は優遇されすぎ」と、子どもを持つ親を「子持ち様」と呼び、彼らの時短勤務や急な帰宅などによる仕事のしわ寄せが来ることを不公平だと批判するSNS投稿などが話題となった。これに対し、子どもがいない人を「子なし貴族」と呼んでマウントを取り合う様子も見られ、20年にわたりネットで火花を散らしてきた「子持ち 対 非子持ち」バトルの何度めかの再燃を遠い目で見る思いだ。
だが今回この問題に、悪意のこもった呼び名ではあるが「子持ち様」という名称が与えられたことで、これまでのバトルとは異色な点が明らかとなった。
これまでは、批判や揶揄の対象は「勝ち犬」のように結婚出産した専業主婦であったり、「子蟻」「キラキラママ」のように、育休取得や時短シフトするなど、仕事も続けながら子育てをする女性――つまり、女性の生き方の選択における「あっち側」と「こっち側」の間で起こる摩擦だったのだ。