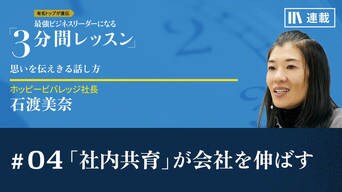ねねの領地は天王寺や玉造などの最重要エリアだった
1592年に、ねねが収入を得ていた地域は、大坂城の周辺です。地図で見ると、ねねは大坂城下を包み込むように、天王寺、平野庄、国分、林寺、湯谷島と、かなり広い地域を所有していたことがわかります。大坂城の南のほう、お城近辺から南部へ向かって、かなりの地域がねね名義の土地として与えられていました。
所領の中でも、大坂城の防衛の面から見ると、天王寺が極めて重要な場所でした。もうひとつ、玉造という村は、違った意味で重要でした。細川忠興、前田利家、浅野長政、さらに千利休といった豪勢な面々が住居を構えていた地域で、商業的な利益よりも人的な関わりという点で、この居城地の地主であることに意味があったのです。
新興商業地となっていた大坂は、この頃からますます発展していきます。大坂と京都の南のほうにある伏見に繋がる道、江戸方面へ向かう道、それぞれの方面へ物流網が張られていきました。大坂からの水陸の交通を要に、人も物も各地に往来していきます。その後、海運は日本海と太平洋に広がり、人々を日本の外の世界へ誘う、地の利を得ていました。
秀吉の跡継ぎを産んだ茶々ら側室と、ねねとの関係
側室と正室のねねの関係はどうだったのでしょうか。次の手紙が、その関係を知るのに適したものなので、長文ですが、現代語訳で一通り読んでみましょう。
1590(天正18)年4月13日に、秀吉が北条氏政、氏直を相手に小田原に詰めている間に、ねねに送ったものです。まずは、ねねが小田原へ使いの人を送っていることへの感謝から始まり、ねねに戦況を伝えます。
何度もこちらに人を送ってくださいました。とても嬉しく思います。小田原では、敵を2、3重に取り卷き、堀や塀を2重に作り、誰一人として逃さない方針です。特に、坂東人国(相模、武蔵、上総、下総、安房、常陸、上野、下野)の者達は籠城しているので、小田原を乾殺し(餓死)にすると、奥州までの地域を平定したことになりとても満足に思います。
日本の3分の1に価するものなので、この場面で、辛抱強く、長い時間がかかっても、しっかりと指令をすることで、この先末長く天下のためによいことをしょうとしているので、今回は剣を振るい、長丁場の戦に持ち込み、兵力も食料も金銀もつぎ込んで、名前が残るようにしてから、凱陣する予定ですので、ご安心ください。このことは、皆々へも伝えてください。
追伸 早々と敵を鳥籠に入れている状態なので、危ない目にはあっておリませんので、ご安心ください。若君が恋しいですが、行く末を見据え、天下を穏やかに平定すべきだと思います。会えない恋しさもありますが、どうかご安心ください。私は、灸も施し、養生しておリます。ご心配なさらないよう。各々へもこのことを伝え、大名たちに女房を呼ばせ、小田原に滞在するよう言いました。
日本の3分の1に価するものなので、この場面で、辛抱強く、長い時間がかかっても、しっかりと指令をすることで、この先末長く天下のためによいことをしょうとしているので、今回は剣を振るい、長丁場の戦に持ち込み、兵力も食料も金銀もつぎ込んで、名前が残るようにしてから、凱陣する予定ですので、ご安心ください。このことは、皆々へも伝えてください。
追伸 早々と敵を鳥籠に入れている状態なので、危ない目にはあっておリませんので、ご安心ください。若君が恋しいですが、行く末を見据え、天下を穏やかに平定すべきだと思います。会えない恋しさもありますが、どうかご安心ください。私は、灸も施し、養生しておリます。ご心配なさらないよう。各々へもこのことを伝え、大名たちに女房を呼ばせ、小田原に滞在するよう言いました。