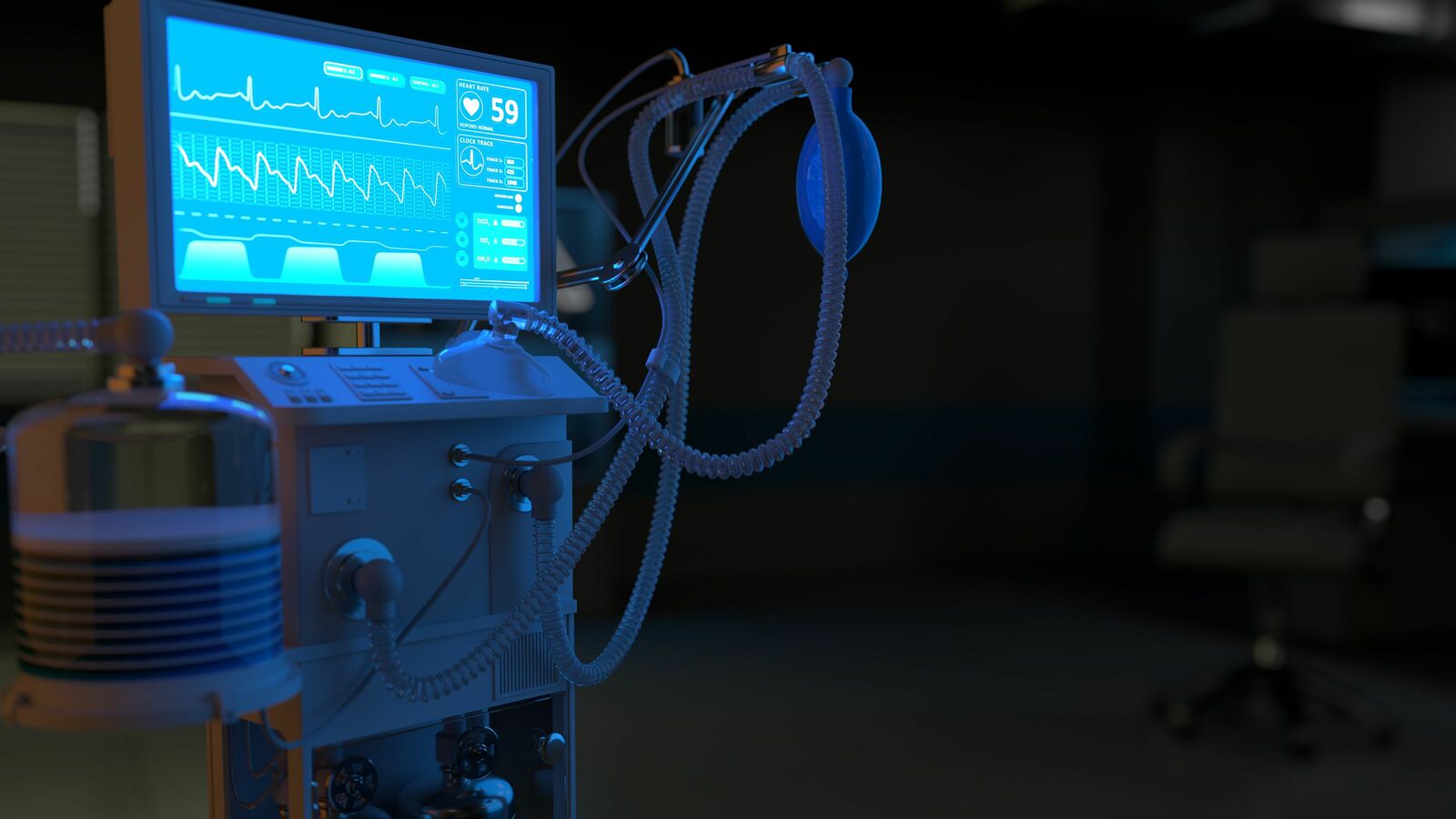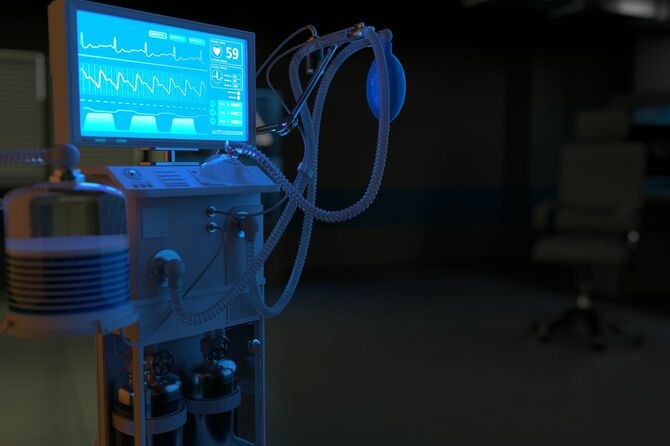関東在住の中野篤さん(仮名・60代・既婚)は、仙台育ちの一人っ子。編集者をしていた妻は53歳ごろから頻繁につまずくように。一方、仙台で一人暮らしの母親は、年齢を重ねるごとに転倒が増え、86歳のときには顔に大あざを作った。中野さんは母親を「ケアハウス」に入所させた。その頃、妻は、「ALS」と診断され、日に日に身体が動かなくなっていき、自発呼吸も難しくなり、人工呼吸器の使用を開始。さらに胃ろうを造設。母親は施設入居後、心不全、肺炎、盲腸炎から派生した敗血症、胃がんステージ4が発覚するも、母親の希望で、最期までケアハウスで過ごすことに。妻が退院すると、本格的な在宅介護生活が始まった――。
母親の逝去
「この度は看取りを受け入れていただきありがとうございます」
2018年、仙台の実家に住む母親は90歳を超え、心不全、肺炎、盲腸炎から派生した敗血症、胃がん(ステージ4)……と次々に病魔に襲われ、終末期病院への転院も考えたが、母親の希望で、ケアハウスに戻ることになった。
病院のソーシャルワーカーから、母親が入居していたケアハウスの寮母長への手紙には、冒頭のように書かれていた。関東地方在住の中野篤さん(仮名・60代)は、「ああ、いよいよ看取るのか」と母親の死を覚悟した。
中野さんは退院やケアハウスへの移動など、すべてをケアハウスのスタッフに一任して関東の自宅に帰り、7年前に国指定の進行性難病であるALS(筋萎縮性側索硬化症)を発症した妻の介護にかかりきりの生活に戻った。
ところが2017年10月。母親が退院して施設へ移る2〜3日前から、中野さんはソワソワ。「退院からケアハウスの部屋のベッドで寝付くまで、母のそばにいてあげたい」と思った中野さんは、妻のヘルパーの会社に相談し、退院日は仙台に終日いられるようにシフトを組んでもらった。
当日、中野さんは朝イチで仙台へ。病室に着くと、もう寮母長やスタッフたちが退院の準備をしていた。そんな中、中野さんの顔を見るなり母親が「篤、また来たの⁉」と大声を上げた。
以前、「あんた誰?」と名前を忘れられてショックを受けていた中野さんは、かつての母親の姿に嬉しさがこみ上げた。
中野さんと母親は、寮母長たちとともにケアハウスに到着。ケアハウスのアイドル犬やスタッフたちが出迎えてくれた。母親は元いた部屋のベッドに就き、2人は最終の新幹線まで過ごした。
「母はあまり喋りませんでしたが、眼力が強く、私に何かを語りかけていました。今思えばたぶん、『さようなら、元気でね』だったのだと思います」
関東に戻った後、2〜3日に1回くらいの頻度で、「危ないから来てください」という電話を受け、ついに同年10月31日午後3時ごろ、「亡くなりました」との連絡があった。
中野さんは、あらかじめ妻の主治医やソーシャルワーカーに母親の状態を説明していたので、母親の逝去を伝えると、翌朝の妻の入院の手配をしてもらうことができた。
翌朝一番に妻とともに大学病院に向かい、病室のベッドに妻が収まるのを見届けてから、準備しておいた荷物を再確認すると、急いで新幹線に飛び乗った。
仙台に着くと、夕方からの葬儀社との打ち合わせにギリギリ滑り込み、その後ようやく母親の顔を見ることができた。すでに棺に収められた母親のまぶたは閉じていたが、口は少し開いていて、何か話したそうに見えた。中野さんは、妻がALSだと分かったときも、気管切開をしたときも涙は出なかったが、このときばかりは涙が溢れ、「ここまで育ててくれてありがとうございました……」とつぶやいていた。