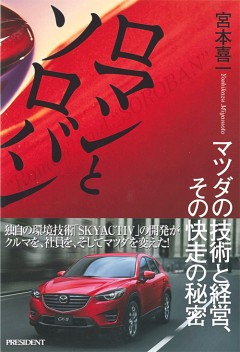マツダのクルマづくりの考えがわかるデザイン
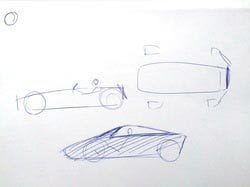
初代ロードスターの発売から四半世紀あまり、本年4月22日、ロードスターの生産累計はついに100万台を突破した。1989年の生産開始以来、27年間で積み上げてきた数字だ。名実ともに“グローバル・カー”と呼ばれる資格十分だ。とはいえ、今回の受賞には、このグローバル・カーに新しい勲章がもうひとつ加わった、というだけでは終わらない、もっと重要な意味があるのだ。
それは、今回のロードスターの受賞によって、マツダが、独自技術のスカイアクティブを核としてこの数年(とくにスカイアクティブの第1号車CX-5を発売した2012年2月以降)展開してきたブランド戦略が成功をおさめ、さらにそれを次の段階に移行できる状況をつくりだしている、この事実が国際的、客観的に証明されたことが、マツダにとって非常に重要なのではないか。
言うまでもなく、ロードスターは現在、マツダのブランドを象徴するいわば“ブランド・アイコン”として位置づけられており、それだけにその戦略を展開発展させるという大きな役割を担っている。この役割を全うさせようと、実は、マツダの経営陣は、今回のロードスターを開発するにあたって、デザイナーに次のような命題を与えた。
「マツダのクルマづくりの考え方がわかるようなデザインにしろ!」
ブランド・アイコンである以上、しごく当然の要求だと言えるだろう。
確かに、今でこそ、ロードスターはマツダのブランドを象徴するモデルと一般的にも捉えられてはいる。しかし、27年前にこのモデルが誕生したときには、マツダ自身に、これを“ブランド・アイコン”にするという明確な意図が必ずしもあったわけではない。
ロードスターが初めて誕生した(エンジニアやファンの間ではその型式からNAと呼ばれている。ちなみに、それ以降の世代はNB、NCとなり、今回受賞した最新モデルはND)のはすでに述べたように1989年。このとき、このオープン2シーターの軽量スポーツカーに与えられていた位置づけは、当時マツダが推進していた販売チャンネルの拡大路線によって生み出された5種類のブランド(マツダ、アンフィニ、オートラマ、オートザム、ユーノス)のひとつ、「ユーノス」のいわば目玉的なモデル、だった。
これが世界的な大ヒット製品となり、1998年の2代目NB(ユーノス・ブランドが廃止されたためマツダ・ロードスターに名称変更)、2005年の3代目NCへとモデルチェンジをしていく過程で、エンジンの排気量はNAの1.6Lから1.8Lそして2.0Lへと拡大していく。デザインも基本的に初代からの流れが継承されていった。