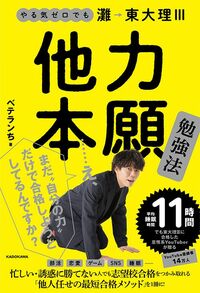自分を客観的に見られる仕組みをつくる
ここまでアウトプットのことを紹介してきたのは、自分で自分を客観的に見られるようになる必要が受験生にはあるからです。アウトプットの結果を振り返るときには、自分を客観視できていることが理想です。そのために、自分の「受験勉強マネージャー」になるようなイメージを持つ必要があります。
アスリートには、その人を客観的に見て、その強み弱みを把握したコーチや監督がいるように、強い人には、自分を客観的に見て修正してくれる他人がいるのです。
受験の場合も、そういう他人がいてくれればいいですが、なによりも、自分が自分のマネージャーになってしまうのが、一番効果的です。
そのために先ほどのフィードバックノートが役立ちます。「この計算、ミスしやすいから、本番では必ずダブルチェックしよう」「この分野の問題をできるようになりたいって言ってるけど、でもこっちの分野の方が弱いから、まずこっちから始めよう」などなど、情報がつまったノートを見ると、優秀なマネージャーのように客観的に自分を分析できて、自分を修正する手掛かりになります。
「受験勉強マネージャー」の仕事にリソースを割く
大学受験では、試験問題が解けるように必死に勉強することが大事だと思われがちです。
しかし、極端なことをいえば、受験のプレイヤーとしての自分を鍛える時間よりも、このマネージャーとしての自分を構築する方にリソースを割いた方が効率的だといえます。
だから、「目標を決めて」「道筋を決めたら」マネージャーとしての自分の能力を高めていくことを第一に考えた方がいいのです。ただがむしゃらに勉強だけを続けるより、1冊の赤本30周するより、「数学はできるようになってきたから、今はそこに集中させよう。地理はあとでいい」「飽きっぽいから予備校ひとつだけじゃなくて、夏期講習は他のところに行こう」など、常に考えながら勉強することが大切なのです。